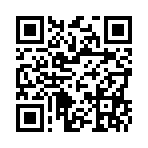2019年12月04日
1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その9
予想はしていたが、エンジンにも自己流の整備が多々あって私を悩ませてくれる・・・
一般の自動車整備にレーサーの整備・・・どちらにもそれぞれのセオリーがあり私と同じ整備士が汗水を流して懸命に努力している。特に走行速度域が極端に上がるレーサーの整備では厳しいまでの質の高さが求められる。
レーサーの世界ではメネジを予めヘリサート加工する事は一般的だ。特殊なステンレス鋼製のネジ山はアルミ製の母材とはケタ違いの耐久性を持ち幾度の脱着にも耐える。その加工途中の思考とは、「どうすれば最も有効な状態に仕上げられるか…」なんだ・・・これは私が加工したモノ。穴の奥行きに可能な限り有効なネジ面を作る事が基本。入れるボルトの様々な状況に耐えられるように気を配る。
このネジ面の位置が見えるかい?・・・このエンジンの場合、全ての場所でその位置は違う。手前に数巻あるモノ、中央に数巻あるモノ、奥の奥に数巻あるモノ、何れの場合にも3巻程度である事が特徴だ。ステンレス製のコイルの数巻分の軽量化を狙うなどと私には到底思えない・・・更にこのエンジンは、ほぼ全てのネジ山にヘリサート加工を施しているから厄介だ・・・
私も流石にこれには参った・・・これを直すとなると一旦削り取りアルゴン溶接で肉盛りし改めてヘリサート加工をやり直す事になる。そんな事をほぼ全ての箇所に出来ると思うかい?・・・残念だがこれらには最低限度の修復を施し使えるモノは使う方針とした。
取り付けられるボルトの端面もこのあり様、もうこれは作業者の性格の問題だ。皆さんが自分の愛車にこんな汚い仕事をされたらと想像してみてくれ・・・
これはブリーザーの取り出し口だが、インチネジの上からミリネジを切っているがとても褒められたモノじゃない・・・
この真相はこうだ・・・ブリーザーのメネジにミリネジでタップを切る→プラグを作ろう→ブラスの丸棒からネジを切ったが六角の加工は出来ない→モノが丸い為につかめない・・・ボルトを真ん中に入れて締められるようにしよう・・・
只、先にボルトが緩んだ場合にはどうするんだい?・・・せめて中央に穴くらい開けなきゃイカンだろ・・・ここは、カムシャフトの端面から取り出すブリーザーの容量不足の改善の為にいじる場合が多いが、今回の原因かは分からない。
で、新しいオーナーのTさんは一般人だから、必要のない過度の整備を控え費用を抑えなきゃイケないとコンセプトを再認識。で、自作されたプラグに二面分のカットをする・・・
こうすれば、スパナで脱着が可能になるし六面加工するよりも安く済む。ネジはミリネジだから二面幅も敢えて14mmとしてやった。
クランクケースとは、元々左右違う金型から鋳造されたものなので、必ず位置を決めてから各部の穴開けがされる。その為にノックピン等が使われる。しかし、このエンジンには2個あるうちの1個がない・・・で、このケースには幾場所かに溶接の修復跡がある。ここもその時の不完全な作業によってピンを取り外したようだ。だがそれではケースの定位置からずれてしまう・・・
普通のカラーなどとは違い、この場合には100分の1ミリ単位の精度でピンを慎重に削る・・・
中央の小さなモノが作り直したピンだ・・・これで左右のケースが他の要因に邪魔される事なくセンター性を維持できるようになる・・・
排気量に伴いメインベアリングへの負荷が増大しボールベアリングでは破損が多発するようになる。1970年代に進むにつれ各社それぞれにローラーベアリングへと移行する・・・
取り外すとケースとの嵌め合いが過去の脱着で傷んでいる事が分かる。これ冷間で取り外す時に出来る傷だ。エンジンをバラそうとしている皆さん、お願いだからここを冷間で外そうとする事はやめてくれ。ここを傷める事だけは絶対にしてはイケないんだ・・・
ノートンツインエンジンには、やはりこのローラーベアリングが適する。耐久性もずば抜けて高く何処まで走っても絶対的な安心感がみなぎる・・・
現行の市販車のエンジンをレース用にする場合、必ずバリや形状の不具合を修正する事は当然だ。だがクラシックカーの世界では禁断の領域だと知って欲しい。どんなにバリが出ていても、どんなに鋳型の形状不良があっても、絶対に削ってはイケない。製造当時の鋳型に敬意をもって「へぇーこのエンジンの鋳型おもしろいねぇ~・・・」なんて会話が将来に渡って続く事がこの世界の醍醐味、一気に価値が下がってしまう・・・
で、このタイミングサイドの内面を削った跡がある。リフト量の多いカムシャフトを入れた場合に接触するところでもあるが、ここをこのような形状に削る事は誠にもって無知の証だ。やってはイケない事の典型だと言っておく・・・
基本的な話に戻すが、これはクランクケースのボトムに位置するエンジンオイル用のストレーナーで異物をオイルポンプを始めラインに流さないためのモノ。この時代のエンジンには現行車のような高分子フィルターは無いから、この金網でこしとるだけでしかない。レースをしようとするエンジンがこんな汚れとは一体どういう事なんだ?・・・これでサーキットコースを走ろうと言うのか?・・・
今回のボトムの作業は大切だからと常に念入りに行うものの、コストとの兼ね合いも大切だ。一般道を走る人に過度の整備は必要のない事。
さりとて無謀な状態をそのまま渡す訳にもいかない・・・使えるところは極力そのまま再使用しどうしてもダメな部分に注力する・・・やるべき作業が出来ずに余計な事ばかりに費用がかさんで行く・・・
「この車両はレースで入賞したから凄く良いものなんですよ・・・」 皆さんもこうした誘い文句の裏側が見えたと思う。残念な事に、このボトムで私が称えたいモノはスチール製のコネクティングロッドだけになってしまったんだ・・・松枝
1975 NORTON COMMANDO 850 Mk3 Roadster プチ報告その6
1965 TRIUMPH T120R プチ報告その4
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その17
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その16
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その15
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その14
1965 TRIUMPH T120R プチ報告その4
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その17
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その16
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その15
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その14
Posted by nunobiki_classics at 01:04
│作業中車両のプチ報告