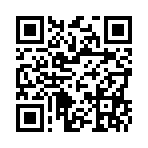2019年07月23日
1968 BSA A65T THUNDERBOLT 大阪市S様 納車整備報告
「布引お手軽倶楽部」1968 BSA A65T Thunderbolt 大阪府S様 完成のご報告です。

「・・・すみません、黒のBSA欲しいんですけど・・・」 エストレアに乗る彼はこれが初めての英国車だ。上背も標準的で一見物静かな彼に適した諸々を吟味する・・・そして相談の結果車両はBSA A65Tとなり、その予算は、「布引お手軽倶楽部偉いぞ堂々の200万円コース!」に決まった。

ここで「布引お手軽倶楽部」のご説明・・・
ここで言う200万円とは、諸費用税など全て込みで200万円と言う明朗会計。で、このコースの場合の車体価格は約170万円程度になる。この170万円の車体価格の枠の中に布引クラシックスとしての安心感を如何に詰め込んでいくのか・・・?ここがポイントだ。 ※お手軽倶楽部はコチラ

そして半年後、オリジナル度の高い上質なサンダーボルトが海を越えてやって来た。「・・・これは良い・・・素晴らしいぞ・・・」開けた途端に感動の出会いだ・・・ ※英国車の輸入販売はコチラ

エンジンは直ぐに始動しそこそこ安定している。電装系統も車体も実用上問題はない。普通ならこのままナンバーをつけて納める事が定石、それなら170万円でも利益が出る。

しかし、A65の場合、必ず見るべき場所がある・・・「大端部のガタの出方が悪いなぁ・・・」 やはりエンジンのボトムが疲労している。重いフライホイールに良く回るエンジンの負荷がここに集まる・・・

比較的ダメージの少ないコネクティングロッドの小端部にもガタがある。日陰の存在的なここもしっかりと交換&修正する。

これはメインベアリングのアウターレース側、シリアルナンバーの入るケースを絶対に傷めてはイケない。必ず十分に加熱し接触面に負荷を掛けずに脱着を遂行する。

ここには大容量のローラーベアリングが使われている。重いクランクシャフト&回転数に耐えるためのA65必須の装備だ。

これはタイミングサイドのメインベアリングで、ここはブッシュで構成される。これを旧式とみるのか先進的とみるのかは皆さん次第だ。

ピストンは75mm径と、このクラス最大の大きさ。焼き付きの跡も無くクリアランスも規定値内である事から各部の修正で対応する・・・

クリアランスの幾分広めのガイド及びバルブもピストン同様に再使用する。シートカット及び擦り合わせを丁寧に行う・・・ピストンにバルブ、これらは170万円に納める為の策だ。

皆さんはエンジン内部の動きには興味はない・・・「グォーーーーーン!」重いフライホイールを持つクランクシャフトがガンガンに廻り続ける・・・「シャカシャカシャカシャカ!」カムシャフトは長いプッシュロッドをこれでもかと突き上げ・・・「カチャカチャカチャカチャ!」ロッカーアームは反力の強いバルブスプリングと戦い・・・「シャーーーーーーー!」75mmの大径のピストンが毎分何千回転と上下運動を繰り返す・・・

しかし、どんなに古い時代に於いてもこれらが正確に作動する事は実は非常に大切な事なんだ。その意味でA65のシリンダーは偉いぞ。この底面の広いどっしとりした鋳鉄製シリンダー、上下で勝手に暴れ廻る部品達の腕を掴み「絶対に離さねーぞっ!」と、微動だにしない・・・これが後に私が語るA65の楽しい走りに直結する要因のひとつなんだ・・・

エンジンの性能を大きく左右するキャブレター、アマル社製930が1968年から採用された。このサンダーボルトはシングルでライトニングはツインキャブとなる。誰しもツインキャブレターが良いと思っているが、本当にそうだとしたら余りにも悲しい。

これはライトニングの930のツインキャブレター。一気筒に一基のそれは主にスロットル開度1/2~全開までに威力を発揮しA65の高性能さに寄与する。しかし、リターンスプリングも倍になりスロットルホルダーを廻す力も倍必要になる・・・要するに重い訳だ。そもそも私はスロットル操作こそモーターサイクルライディングの基礎だと皆さんに言ってきた。そして、その進化から現行車ではスッカンスッカンに軽くなる・・・その観点から倍になったこの重さは不利であるばかりか正確さや楽しさをも奪い兼ねない。

対してこれはサンダーボルトのシングルキャブレター、勿論走りはおとなしいモノにはなるもののスプリングの反力は半分とすこぶる軽い。これが正確なスロットル操作を実現し楽しい走りに直結する。手の小さな日本人が重いスロットルを握りしめ高性能さを求める事も英国車の楽しさ?・・・対して走り始めから夕方の帰宅迄、常に楽しく且つ緩やかなスロットル操作が可能なサンダーボルトの走りもそれに変わらず価値あるモノ?・・・どちらに優劣があるとは言ってない。何れにしも個人の目的に合わせて車種を選択すべし!これが大切。英国車の場合、キャブレターの個数を変える時にはシリンダーヘッドも同時に交換する必要があるからだ。

小さくまとめると、今回のサンダーボルトを170万円に納める為のポイントとは?・・・エンジンボトムの作業を優先したところだ。無論私的には辛くなるけれどオーナーの将来を鑑みベストだと判断した上での事だ・・・エンジンとはボトムの状態が何よりも大切。年老いた爺さんに血気盛んな若者を「おんぶ」させるなんて誰が出来る?と言いたい・・・トップなら何れお小遣いを貯めて作業は出来るじゃないか・・・

続いて、お手軽倶楽部で重視するのは電装系統だ。これが路上でトラブルと顧客は対応できないから最重要項目としている・・・メインハーネスを始め全てを刷新している。そして、これは発電機のステーターコイルで大切な役目を担う。で、元のモノを精査すると交換が望ましい、同時に10Aと容量を上げたルーカス社製RM21を選択した。 ※大切な電気の話はコチラ

そしてルーカス社製6CAのコンタクトポイントブレーカー、エンジンに火花を飛ばす為の指令装置、その中に有るアジャスターだ。以前の4CAに較べ各部の調整を独立して取れるようになった反面スクリュー等の数は多い。半世紀以上も経つとスクリューの痛みも進みこのように工具で廻せなくなる。

このような誰も交換しないモノを徹底して復元する辺りが正に布引流・・・以後の作業が効率的になるばかりか後世に渡り正しいモノとして維持出来る訳だ。

さあ、ここからがA65の本番だ。BSAのAシリーズを語る上で外せないのがフレーム剛性の高さ。見ての通りの強靭さはBSA社のアイデンティティーだ。

これはスイングアームのピボット部分だが当時ではあり得ない位の幅がある。両手をすぼめているよりも肩幅位に広げた方が断然モノは保持し易い。当シリーズの走りの良さの正にここが原点なんだ!

モーターサイクルの最重要箇所であるステアリング。ハンドルを離せば「・・・ストンッ・・・ストンッ・・・」と勝手に曲がり切る自由度がなければ楽しい走りは得られない・・・

この幾分丸みを帯びたスイングアームは、暗にそのバランスを語っている・・・高剛性なフレームに幾分優し気なスイングアーム・・・それに伝わり来るA65の元気なエンジン出力を受け止める時・・・現行車の高性能な話しとはかけ離れている事は無論知っている。しかし、敢えて語るがここの「シナリ」が実用速度域でどれ程の幸せを我々に与えてくれているのか・・・現行車ライダーには知る由もないんだ。

この時代のフロントフォークなどゴミだと現代人は言う・・・本当にそうかな?・・・自分の腕の無さを時代に転嫁する事はよせ・・・このカートリッジ式ダンパーは「あんたの腕次第なんじやないの?・・・」と語っている・・・

そしてエンジンをかける時が来た。オイルにガソリンを入れ、潤滑系統が機能している事を確認し火を入れる 「ズッ・・・ズドゥドゥドゥーーーーン!・・・」 充電系統の作動を確認し一旦火を止める・・・

そして再びエンジンを始動し今度はイグニッションのタイミングを調整し、最後にキャブレターの調整をとる 「・・・ズドゥドゥドゥーーーーン!・・・ズンズンズンズンズン・・・」 こうして新規検査受けの準備は整った・・・

翌日、新規検査を受ける。通常の検査ラインを通り新規検査へ出向き、そして最後に新規登録だ。今回は何時にも増して順調に事が進んだ・・・

ところで、このサンダーボルトに跨り走っていると私はいつもと違う事が頭に浮かんで来る・・・皆さんはもう聞き飽きている私の口癖「人生は一度きりなんだぞ・・・」 これを機会に本気で頭に描いて欲しい・・・

少なくとも私の店に来てくれる顧客は少なからず自分の人生と葛藤している。彼女がいて、家庭があって、仕事もある・・・全てが上手く行く訳じゃない、いや全てが上手く行かないと言った方が正しいかもしれない・・・

気がつけば何年もの時間が過ぎている事にハッとする自分に焦ってばかり・・・だけれども、男ってバイクが好きなんだ!それに嘘をついて生きるのはもうやめろと言っている。走りたければ走れよ!乗りたければ乗れよ!それが男の子の進むべき道じゃないのか?・・・自分を男だと思うなら 「人生とは一度きりなんだぞ・・・」 真面目に考えて欲しいと思うんだ・・・

こうしてサンダーボルトに跨る時、私は違う人間になれる。何にも関わらなくてもいい自由な時間が私を強烈に守ってくれる・・・それが本当に嬉しくて、その為に走っている気がする・・・

これでSさんの為の「布引お手軽倶楽部偉いぞ堂々の200万円コース!」車体価格170万円の枠の中、私も精一杯に尽力した。電装系統を刷新し、車体を整備し、エンジンのボトムを中心に出来得る限りの作業を施した。ビギナーがデビューするにあたって見た目も中身も十二分なモノを用意したつもりだ・・・

そしてサンダーボルトにもう一度命を吹き込めた事・・・これが私は何より嬉しい・・・どうだい?この凛としたA65の雄姿を見て欲しい・・・遠くアメリカから強制的に連れて来られ不安に怯えていたサンダーボルトも今は明るく笑顔を取り戻した。その走っている横顔を見ながら私は言ったんだ 「・・・おーいっ!ずっと一緒だぞっ!・・・」 すると 「・・・うん、ついてくーっ!・・・」 そう風の中から聞こえたんだ・・・

そして、今回は試運転の報告はしない。生粋の2スト乗りだった私が24才の時に心動かされた思い出のモーターサイクルであるA65・・・それが如何に魅力に溢れたマシンなのか別の機会に報告したいと思っている・・・ 2019/07/23 布引クラシックス 社長 松枝
試運転コースは以下です。

参考記録
一般道走行距離・・・・・・・・298.1km
高速道路走行距離・・・・・・23.2km
総走行距離・・・・・・・・・・・・321.3km
使用燃料(プレミアム)・・・・12.72L
燃費・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.3km/h
燃料タンク容量・・・・・・・・・約9L
リザーブ容量・・・・・・・・・・・約1.5L
航続距離の目安・・・・・・・・約185km

「・・・すみません、黒のBSA欲しいんですけど・・・」 エストレアに乗る彼はこれが初めての英国車だ。上背も標準的で一見物静かな彼に適した諸々を吟味する・・・そして相談の結果車両はBSA A65Tとなり、その予算は、「布引お手軽倶楽部偉いぞ堂々の200万円コース!」に決まった。
ここで「布引お手軽倶楽部」のご説明・・・
ここで言う200万円とは、諸費用税など全て込みで200万円と言う明朗会計。で、このコースの場合の車体価格は約170万円程度になる。この170万円の車体価格の枠の中に布引クラシックスとしての安心感を如何に詰め込んでいくのか・・・?ここがポイントだ。 ※お手軽倶楽部はコチラ
そして半年後、オリジナル度の高い上質なサンダーボルトが海を越えてやって来た。「・・・これは良い・・・素晴らしいぞ・・・」開けた途端に感動の出会いだ・・・ ※英国車の輸入販売はコチラ
エンジンは直ぐに始動しそこそこ安定している。電装系統も車体も実用上問題はない。普通ならこのままナンバーをつけて納める事が定石、それなら170万円でも利益が出る。
しかし、A65の場合、必ず見るべき場所がある・・・「大端部のガタの出方が悪いなぁ・・・」 やはりエンジンのボトムが疲労している。重いフライホイールに良く回るエンジンの負荷がここに集まる・・・
比較的ダメージの少ないコネクティングロッドの小端部にもガタがある。日陰の存在的なここもしっかりと交換&修正する。
これはメインベアリングのアウターレース側、シリアルナンバーの入るケースを絶対に傷めてはイケない。必ず十分に加熱し接触面に負荷を掛けずに脱着を遂行する。
ここには大容量のローラーベアリングが使われている。重いクランクシャフト&回転数に耐えるためのA65必須の装備だ。
これはタイミングサイドのメインベアリングで、ここはブッシュで構成される。これを旧式とみるのか先進的とみるのかは皆さん次第だ。
ピストンは75mm径と、このクラス最大の大きさ。焼き付きの跡も無くクリアランスも規定値内である事から各部の修正で対応する・・・
クリアランスの幾分広めのガイド及びバルブもピストン同様に再使用する。シートカット及び擦り合わせを丁寧に行う・・・ピストンにバルブ、これらは170万円に納める為の策だ。
皆さんはエンジン内部の動きには興味はない・・・「グォーーーーーン!」重いフライホイールを持つクランクシャフトがガンガンに廻り続ける・・・「シャカシャカシャカシャカ!」カムシャフトは長いプッシュロッドをこれでもかと突き上げ・・・「カチャカチャカチャカチャ!」ロッカーアームは反力の強いバルブスプリングと戦い・・・「シャーーーーーーー!」75mmの大径のピストンが毎分何千回転と上下運動を繰り返す・・・
しかし、どんなに古い時代に於いてもこれらが正確に作動する事は実は非常に大切な事なんだ。その意味でA65のシリンダーは偉いぞ。この底面の広いどっしとりした鋳鉄製シリンダー、上下で勝手に暴れ廻る部品達の腕を掴み「絶対に離さねーぞっ!」と、微動だにしない・・・これが後に私が語るA65の楽しい走りに直結する要因のひとつなんだ・・・
エンジンの性能を大きく左右するキャブレター、アマル社製930が1968年から採用された。このサンダーボルトはシングルでライトニングはツインキャブとなる。誰しもツインキャブレターが良いと思っているが、本当にそうだとしたら余りにも悲しい。
これはライトニングの930のツインキャブレター。一気筒に一基のそれは主にスロットル開度1/2~全開までに威力を発揮しA65の高性能さに寄与する。しかし、リターンスプリングも倍になりスロットルホルダーを廻す力も倍必要になる・・・要するに重い訳だ。そもそも私はスロットル操作こそモーターサイクルライディングの基礎だと皆さんに言ってきた。そして、その進化から現行車ではスッカンスッカンに軽くなる・・・その観点から倍になったこの重さは不利であるばかりか正確さや楽しさをも奪い兼ねない。
対してこれはサンダーボルトのシングルキャブレター、勿論走りはおとなしいモノにはなるもののスプリングの反力は半分とすこぶる軽い。これが正確なスロットル操作を実現し楽しい走りに直結する。手の小さな日本人が重いスロットルを握りしめ高性能さを求める事も英国車の楽しさ?・・・対して走り始めから夕方の帰宅迄、常に楽しく且つ緩やかなスロットル操作が可能なサンダーボルトの走りもそれに変わらず価値あるモノ?・・・どちらに優劣があるとは言ってない。何れにしも個人の目的に合わせて車種を選択すべし!これが大切。英国車の場合、キャブレターの個数を変える時にはシリンダーヘッドも同時に交換する必要があるからだ。
小さくまとめると、今回のサンダーボルトを170万円に納める為のポイントとは?・・・エンジンボトムの作業を優先したところだ。無論私的には辛くなるけれどオーナーの将来を鑑みベストだと判断した上での事だ・・・エンジンとはボトムの状態が何よりも大切。年老いた爺さんに血気盛んな若者を「おんぶ」させるなんて誰が出来る?と言いたい・・・トップなら何れお小遣いを貯めて作業は出来るじゃないか・・・
続いて、お手軽倶楽部で重視するのは電装系統だ。これが路上でトラブルと顧客は対応できないから最重要項目としている・・・メインハーネスを始め全てを刷新している。そして、これは発電機のステーターコイルで大切な役目を担う。で、元のモノを精査すると交換が望ましい、同時に10Aと容量を上げたルーカス社製RM21を選択した。 ※大切な電気の話はコチラ
そしてルーカス社製6CAのコンタクトポイントブレーカー、エンジンに火花を飛ばす為の指令装置、その中に有るアジャスターだ。以前の4CAに較べ各部の調整を独立して取れるようになった反面スクリュー等の数は多い。半世紀以上も経つとスクリューの痛みも進みこのように工具で廻せなくなる。
このような誰も交換しないモノを徹底して復元する辺りが正に布引流・・・以後の作業が効率的になるばかりか後世に渡り正しいモノとして維持出来る訳だ。
さあ、ここからがA65の本番だ。BSAのAシリーズを語る上で外せないのがフレーム剛性の高さ。見ての通りの強靭さはBSA社のアイデンティティーだ。
これはスイングアームのピボット部分だが当時ではあり得ない位の幅がある。両手をすぼめているよりも肩幅位に広げた方が断然モノは保持し易い。当シリーズの走りの良さの正にここが原点なんだ!
モーターサイクルの最重要箇所であるステアリング。ハンドルを離せば「・・・ストンッ・・・ストンッ・・・」と勝手に曲がり切る自由度がなければ楽しい走りは得られない・・・
この幾分丸みを帯びたスイングアームは、暗にそのバランスを語っている・・・高剛性なフレームに幾分優し気なスイングアーム・・・それに伝わり来るA65の元気なエンジン出力を受け止める時・・・現行車の高性能な話しとはかけ離れている事は無論知っている。しかし、敢えて語るがここの「シナリ」が実用速度域でどれ程の幸せを我々に与えてくれているのか・・・現行車ライダーには知る由もないんだ。
この時代のフロントフォークなどゴミだと現代人は言う・・・本当にそうかな?・・・自分の腕の無さを時代に転嫁する事はよせ・・・このカートリッジ式ダンパーは「あんたの腕次第なんじやないの?・・・」と語っている・・・
そしてエンジンをかける時が来た。オイルにガソリンを入れ、潤滑系統が機能している事を確認し火を入れる 「ズッ・・・ズドゥドゥドゥーーーーン!・・・」 充電系統の作動を確認し一旦火を止める・・・
そして再びエンジンを始動し今度はイグニッションのタイミングを調整し、最後にキャブレターの調整をとる 「・・・ズドゥドゥドゥーーーーン!・・・ズンズンズンズンズン・・・」 こうして新規検査受けの準備は整った・・・
翌日、新規検査を受ける。通常の検査ラインを通り新規検査へ出向き、そして最後に新規登録だ。今回は何時にも増して順調に事が進んだ・・・
ところで、このサンダーボルトに跨り走っていると私はいつもと違う事が頭に浮かんで来る・・・皆さんはもう聞き飽きている私の口癖「人生は一度きりなんだぞ・・・」 これを機会に本気で頭に描いて欲しい・・・

少なくとも私の店に来てくれる顧客は少なからず自分の人生と葛藤している。彼女がいて、家庭があって、仕事もある・・・全てが上手く行く訳じゃない、いや全てが上手く行かないと言った方が正しいかもしれない・・・

気がつけば何年もの時間が過ぎている事にハッとする自分に焦ってばかり・・・だけれども、男ってバイクが好きなんだ!それに嘘をついて生きるのはもうやめろと言っている。走りたければ走れよ!乗りたければ乗れよ!それが男の子の進むべき道じゃないのか?・・・自分を男だと思うなら 「人生とは一度きりなんだぞ・・・」 真面目に考えて欲しいと思うんだ・・・

こうしてサンダーボルトに跨る時、私は違う人間になれる。何にも関わらなくてもいい自由な時間が私を強烈に守ってくれる・・・それが本当に嬉しくて、その為に走っている気がする・・・
これでSさんの為の「布引お手軽倶楽部偉いぞ堂々の200万円コース!」車体価格170万円の枠の中、私も精一杯に尽力した。電装系統を刷新し、車体を整備し、エンジンのボトムを中心に出来得る限りの作業を施した。ビギナーがデビューするにあたって見た目も中身も十二分なモノを用意したつもりだ・・・

そしてサンダーボルトにもう一度命を吹き込めた事・・・これが私は何より嬉しい・・・どうだい?この凛としたA65の雄姿を見て欲しい・・・遠くアメリカから強制的に連れて来られ不安に怯えていたサンダーボルトも今は明るく笑顔を取り戻した。その走っている横顔を見ながら私は言ったんだ 「・・・おーいっ!ずっと一緒だぞっ!・・・」 すると 「・・・うん、ついてくーっ!・・・」 そう風の中から聞こえたんだ・・・

そして、今回は試運転の報告はしない。生粋の2スト乗りだった私が24才の時に心動かされた思い出のモーターサイクルであるA65・・・それが如何に魅力に溢れたマシンなのか別の機会に報告したいと思っている・・・ 2019/07/23 布引クラシックス 社長 松枝
試運転コースは以下です。
参考記録
一般道走行距離・・・・・・・・298.1km
高速道路走行距離・・・・・・23.2km
総走行距離・・・・・・・・・・・・321.3km
使用燃料(プレミアム)・・・・12.72L
燃費・・・・・・・・・・・・・・・・・・25.3km/h
燃料タンク容量・・・・・・・・・約9L
リザーブ容量・・・・・・・・・・・約1.5L
航続距離の目安・・・・・・・・約185km
Posted by nunobiki_classics at
23:24
│作業完成報告 BSA
2019年03月03日
1970 BSA A65L Lightning 愛知県Y様
1962年にデビューするA65はシングルキャブレターを持つサンダーボルト系とツインキャブレターを持つライトニング系のツーラインナップ。サンダーボルトは堅実な路線を歩み、ライトニング系は後にスピットファイアにホーネット等へと派生する。高剛性な車体にパワフルなエンジン性能は北米での高評価を維持するものの台頭するメードインジャパンに屈し1972年トライアンフブランドよりも先に消える。で、今回のライトニングは初代モデルの最終年型、ロイヤルブルーにクロームドされた2ガロンタンクが美しいナイスモデルだ。
A65の特徴は何と言ってもクランクシャフト廻りだ。容量の大きなフライホイールに幾分短めのコネクティングロッドが着く。
そのクランクシャフトを包み込むクランクケースは更に影響している。薄いペラペラのトライアンフ系とは対照的に厚くがっしりと出来ている。
裾の広いシリンダーは見るからに剛性が高く激しい動きにも微動だにしない…
プライマリ系統もしかり、軸間距離が短くスリーロウズされたプライマリーチェーンの剛性は高く正に正確にパワーを伝える陰の立役者だ。
こうしたパワーを正確に出し切るA65のエンジンを、更に有効なモノにしているのが車体だ。BSAらしいレイアウトからしっかりとエンジンの出力を路面に伝える意思が見て取れる。
「グッ・・・ズッババババァ・・・・・ン!・・・」完成したライトニングをいつものように試運転する。軽いスターターレバーから始動性は容易だ。但し、遊びを取ってはいけない、レバーを上から下までフルに使う事がコツだ。
「ズバッバッバッバッバッバッ・・・カッコン・・・ズバッバッバッ・・・」走りだせばとにかく楽しい。剛性の高いクランクケースに元気な出力がしっかりと後輪を廻す様が感じられる。速度が上がる度に、スロットルを大きく開ける度にワクワクする・・・走る事が何たるかを知る者ならではの領域だ。
剛性が高く元気なエンジン特性・・・しっかりとパワーを受け止める車体・・・中央に質量を集めたレイアウト・・・個性あふれる外装の中に実はこうした先進的な設計思想が隠されている。走る事を邪魔する不快な成分を極力排除し運転自体に集中できるクルマづくり・・・それはある意味バーミンガムスモールアーム社の中核モデルとして後世に伝えたかった最後のメッセージじゃないかと私は思うんだ・・・
そして、オーナーのYさんが引取に来てくれましたよ。エンジンをかけてもらいエンジンを温めているところです・・・彼はとても良い人、ベテランらしい振る舞いが良いですね。
トランスポーターにライトニングを積み込みました。ちゃんと傷が入らないように気遣ってくれてますね・・・製作者としてはチョー嬉しいです!
そして、愛知県まで自走で帰って行かれました・・・ 「大事にしておくれよ・・・Yさんありがとうございました。これからライトニングと共に人生楽しんでくださいよ。人生は一度きり!どうせ生きるなら楽しまなきゃ!・・・」 また、いつかどこかで会える日を楽しみにお見送り致しましたよ・・・2019/02/11 布引クラシックス 松枝
試運転コース
参考記録
一般道走行距離・・・・・203.3km
使用ガソリン・・・・・・・・・8.56L(ハイオク)
燃費・・・・・・・・・・・・・・・23.75km/L
Posted by nunobiki_classics at
15:48
│作業完成報告 BSA
2019年01月02日
1961 BSA A10 RoyalTurist 納車整備報告 オーナー大阪市H様
先ずBSA A10を簡潔に説明しよう・・・1947年にA7(500ccツインモデル)がデビュー、続く1950年にA10(650ccツインモデル)がゴールデンフラッシュ系としてスタート、1953年スポーツモデルであるスーパーフラッシュ系が新たに加わる2ラインナップ。前者は北米で安定したセールスを維持し、後者はロードロケット、スピットファイアにロケットゴールドスター等へと派生し共に1963年に生産が終わる。そして、今回のA10RTは1960年に名称が付加された北米専用モデル「ゴールドフラッシュロイヤルツーリスト」だ。
アメリカから良いモノがあると連絡を受け早速輸入した。神戸税関で通関手続きを終え工場で開梱する。各部を点検しエンジンをかけ試しに走ってみる 「うん・・・いいんじゃないか・・・」 で、今回はオーナーと相談の上、機関以外の作業を行い新規検査を受け納める事とした。
英国車の整備とは、先ず油まみれの車体を徹底的に清掃する事から始まる。次に出来るだけ奥の奥から仕事を始める事。現行車と違い容易に交換する事が出来ないこうしたプライマリーチェーンケースの裏側には必ず完全な整備を施してやる。
プライマリーチェーンは単列式で1950年代を踏襲している。ここでの注意点は走行中にラフなスロットル操作を繰り返す事。加速する時には一旦プライマリーチェーンの弛みをとり、それから本格的にスロットルを開けていく癖を身に着けて欲しい。
クランクシャフトエンドにはエンジンとギアボックス間との衝撃を和らげるスプリング式の緩衝装置が見える(前の写真にスプリング見えます)。波状の合わせ面がバネの力に打ち勝つと回転し双方が離れバネを縮ませる方向に移動しようとし衝撃を緩衝する。これも1950年代で終わりを告げ軽量小型のラバー式に変わる。
これはオイルが空の状態で走り続けたクラッチスプロケット・・・そもそも皆さんはプライマリーチェーンオイルの交換をどのように実践しているんだろうか?…思うにかなり適当だ。ここのオイル量はどれもコップ一杯程度。更にドライブチェーンへの給油やシール材にフェルトを使うなど基本的に減少して行く。よってここのオイル交換とは常にオイルの量を一定に保つ為の行為。エンジンオイルと同時に交換する事は英国車乗りの常識だ。
エンジンを走らせる前にバルブクリアランスの調整は必須。英国車のバルブ廻りは弱いからせめて自分の手で触りアジャストしその感触を憶えることが大切。後の不具合や状況の判断に必ず役に立つ。
中央に見えルーカス社製のK2系マグネトーは戦火に於ける命綱でもあった。点火装置は独立し他の回路に影響は受けない。信頼性も高く始動性も良い。但し機械式のブレーカーを使うので定期的なメンテナンスは必要だ。
向かって左がマグネトーの裏側にある丸い進角装置。これは年式やモデルによって固定式と自動式がありこのロイヤルツーリストはオートアドバンスが使われる。そしてクランク軸の下にオイルポンプがあり、右上は発電用の3ELルーカス社製ダイナモへと続く駆動用のチェーンでここにエンジンオイルは使わない。何れも頭脳的な設計に好感が持てる。
これはクラッチのアジャストボルトとプッシュロッドを引っ張り出してところだ。クラッチレバーを握ればこのアジャストボルトがロッドを押し反対側にあるクラッチスプリングを押しクラッチディスクは離れる。ここは回転数の違うモノ同志が接触するからこうしてボールを入れて摩耗を極力減らす工夫となっている。但し、耐久性が低く作動していない場合が実に多い。強い荷重を掛けたうえでの作動の観察が必要だ。
キャブレターはアマル社製389/48。二桁の枝番はモデル固有のナンバーで製造時に装着されていたか否かの判断材料となる。48はこの年式のA10のもので正規のオリジナル品だ。それが今でも現役で使える状態だから是が非でも調子を出してやる。
これは当時のフロートバルブでプラスチック製だ。だが、これが曲者。ガソリンを止める能力が著しく低い。よって如何なる場合にも再使用は不可だ。
写真の右上がプラスチック製とブラス製のフロートバルブで、基本的にシート側とセットの交換が望ましい。で、左下が新旧のフロート。右側のブラス製からプラスチック製へと変わる。但し、ここはセオリーに反し新しいから良いと言えはしない、一度それぞれを浮かせてみればその意外性に驚くはずだ。
ぺトロールラインは英国車に於ける風情。質の高いモノを作る時の大切なアクセサリーでもある。
この時、モデルや時代的背景を考慮する事が必要。A10の場合はこの景色が正に正しくなる。仮にクリアー色のホースを使いご満悦になっていたとする、これが全くのナンセンス。時代的に有り得ない素材を使い鼻高々になっているなんぞ作り手としての恥さらしだ。
1950年代の英国車の魅力は隠れた場所にも多い。当時のドライブチェーンの信頼性は低くモーターサイクルのアキレス腱と言える代物…
そこには英国の雨や霧から守る為の見事な工作が残る。これほど密着したスチール製の部品を量産車に使う事など現代ではあり得ない・・・けれど悲しいかな整備性が悪いと簡単に捨てられてしまう…
だが私は意地でもこのカバー達を残してやる。皆さんも自分のA10にこのタイプのカバーが着いているなら、是非今一度見返してみるべきだ。
エンジンを分解しない場合にも電装系統に完全な作業を施すことが必須だ。この他必要なな作業を経て車両は完成した・・・
海外の車両を日本国内で走らせる場合には並行輸入申請を行い書類審査を受け、更に新規検査に新規登録を受ける必要がある。単に車体を輸入したからといっても登録すら出来ない場合があるって事を皆さんには言っておく。そして神戸の陸運局で予備検査を受けた後、なにわの検査場で新規登録を済ませ、晴れて日本の公道上を走れる合法的な車両となった。
いよいよ私の楽しみにしていた試運転だ。「ズッズッ・・・ズッドロローン・・・ズルッルルルルルル・・・」 エンジンを適切に暖める。そしてシフトペダルをかき上げローギアに入れた。「ココンッ・・・ズッズッズッズッズッズッ・・・」
「カコンッ・・・ズッズッズッズッズッズッ・・・」シフトペダルを踏み込みセカンドギアに入れ更にサードギアへと踏み込む「クンッ・・・ズバッズバッズバッズバッ・・・」 更に一段踏み込みトップギアへと入れた・・・「コンッ・・・ズッズッズッズッズッズッズッ・・・」 車速は50マイル・・・なんとも爽やかな風に包まれる・・・
走り続けるとコーナーが近づいてくる 「・・・ズッズッズッズッズッズッズッ・・・」 スロットルを戻し、リアブレーキを上手に当て減速し備える・・・車体を傾けると 「・・・ズッドゥーーン・・・シャーーーーーーーッン・・・」 完璧な美しいラインを描いてA10は旋回する・・・
ところがA10自ら「もっとスロットルを開けてみなよ・・・」と言ってくる。ならばシートの着座位置を変えステップを踏みかえ幾分気合を入れて走ってみる・・・コーナーに入るとっ! 「・・・ズッドゥーーン・・・シャーーーーーーーッン・・・ズッズッズッズッ・・・ズッズッズバッバッバッバッバッバッ!・・・」 楽しい、めちゃ楽しい、「だから言ったろ、僕は走れるって・・・」 と、A10が私に言った。今年の私は忙しく個人的な旅に一度も出掛けないままだから、少し走らせたもらった・・・試運転の終わりにこのA10の良さをもっともっと引き出してみたいと思う程に未だ々走り続けていたかったんだ…
このような高い性能を秘めたA10を北米市場が放っておくはずはなく、常に安定したセールスを記録したと伝えた。皆さんは意識せずともモーターサイクル発祥の欧米での要求は我々日本人よりも遥かに高くそこでの評価は裏付け無くして得られない。
確かに古典的なデザインは確かな走りに直結しないかもしれない。だが、一度走りだせばどのような条件にも応えて見せる。ゆっくりと走る事も、ズバーンッと走る事も、その両方にとても質の高い走りを見せる。エンジンの高い剛性が少ない出力を効率よく伝えスロットル操作を正しく反映させそれが楽しさに直結する。同じく高い車体の剛性が正しいサスペンションの動きを可能にし路面を追従させそれが抜群の安心感を生む。更にその両者が相まって本来必要な操縦性能とはこうなんだと言わんばかりの走りを見せてくれる・・・
そして忘れてはならない事は、1950年代の英国車らしさに溢れ魅力もだ。ルーカス社製のマグネトーや6ボルトのダイナモ。プリユニット式のエンジンに前後19インチのサラブレットな足回り・・・そしてクロノメトリックのスピードメーター…このような後の時代にことごとく排除されてしまった過去の遺物の集合体であっても見事な走りみせてくれる、と同時に高い趣味性をも持ち合わせていること。古い機械を理解し自ら率先して相棒の面倒を見る気の有る者なら必ずや生涯の友になる。この古典的な車体の中に多くの魅力が隠されているんだと私がドーン!と保証してやる。たった100キロ足らず走っただけで手放せなくなるこのA10は文句なく素晴らしいモーターサイクルだと私が断言してやる・・・
後日オーナーのH氏からのメールが届きましたよ。
「今日(1/4)、白浜まで行ってきました!
ほとんど高速でしたが往復約300KM、絶好調です!!
乗っていてスゴく楽しいです。なんとも気持ちのいいバイクです!
CB750よりA10の方が自分には合ってる感じがして。
ホントにありがとう。また一緒にツーリング行こう!!」
彼は以前、ホンダのCB750K1を乗ってた伝説の全開ライダー。
嬉しい言葉を頂きましたよ。
ホンダCB750の作業はコチラです。
参考記録
一般道走行距離・・・・・91.9km
ガソリン使用量・・・・・・4.03L (無鉛ハイオク)
燃費・・・・・・・・・・・・・・・22.8km/L
Posted by nunobiki_classics at
00:54
│作業完成報告 BSA
2017年10月29日
1970 BSA A65L Lightning 納車報告
今回直輸入したA65L、開梱すると47年前にタイムスリップしたような姿に唖然とする・・・実走行たったの2500マイル、機関から配線から1970年そのまま・・・あくまで時代感を保存するかの如く作業を始めた。
早速、クランクシャフトを調べる。振れもオイルラインの汚れも無くほぼ未使用状態。そして、スマートな形状のカウンターウエイトを持つ反面フライホイールは巨大だ。
実のところA65は75mm×74mmのボアストロークを持ち、他社の650㏄ツインエンジンとは一線を画す。360度クランク、短いコネクティングロッド、ショートストロークレイアウト、重いフライホイール・・・これがA65の特徴だ。
このピストンは勿論オリジナル品で一度の焼き付きもないグッドコンディション。無論リプレイス品よりも古典的であるけれど、熱的変化を感じ取る事や、オイルの焼ける匂いを知るって事は英車乗りのとして大切な財産になる。
一度のボーリング加工も受けてないシリンダーの摺動面はメーカー出荷時の粗いホーニングラインが残る。そして、底面が広くどっしりとした形状は上下の振れに圧倒的に強い。
シリンダーヘッドには必ずバルブを保持するバルブガイドがある。これがどの英国車も弱く、少ない走行距離でもガタが出る。4本共に抜き取り、100分の1mm単位で丁寧にリーマー加工を施し完全なクリアランスを持たせた。
バルブの当たりは意外にも粗く現行車から見るとやってないも同然だ。只、廻ってしまえばその影響は実感し辛く平然と走れる。只、実際に作業するとなると、これがどうしても正確に当たりを出してしまうんだな・・・
A65のギアは素晴らしいぞ。部品の多くを分解せずに脱着出来るカートリッジ式でその出来栄えも良い。但し、シフトシステムは古典的でストロークも長く剛性も低い。この辺りは使う者が機構を理解した上で操作したい。
ギア間の接続は、このように大きなドッグを用いトライアンフとの差別化を図る。各メーカーが勝手気ままに設計した時代に終わりを告げ世界標準に進もうとする非常に興味深い箇所なんだ。
これはエンジンのタイミングサイド。各軸間の距離が近くなり、更に各々の壁が厚くしっかりと出来ているのが分かるだろうか?
こちらがドライブサイド、クランクケースの全てを舐めるように見てみよう・・・他の英国車に比べて剛性の高さは一目瞭然、これがA65の特性の源だと知っておこう・・・(※一番大事なところ)
右側はクラッチ、左は発電用のルーカス社製RМ19。それをつなぐのはスリーロウズのプライマリーチェーン。この容量の大きなチェーンと軸間の短さに高剛性なクランクケース・・・これが味噌なんだ・・・
このピボット部は大切だから入念に見る。全てを洗浄しガタを確認し新しくグリスを入れ替える。賢いモーターサイクリストならステアリングとここの働きを理解して走らせている・・・さて、皆さんは如何なものだろうか・・・?
これは50年物のフロントフォークオイルで粘度はシングル20番だ。水分や空気と混ざり正にエマルジョン状態、もうオイルとは言えない代物だ。だが、笑っている場合じゃない。皆さんはフロントフォークのオイルを何時換えた?定期的に交換すべきモノだと知っているだろ・・・
ここはモーターサイクルの要、リジットであろうがチョッパーであろうが、どんなモーターサイクルでも車体の要だ。・・・コーナーが近づいてくる・・・車体をスッと傾けた時・・・ここのベアリンクがどう動いているのか?・・・自分の感覚で感じ取ってみよう・・・きっと新たな境地を見い出せるはずだ。
これがA65のフレームだ。車体中央部の剛性がすこぶる高められているのが分かる。エンジンプレートを屈指して軽く最低限度の剛性を確保するトライアンフユニット650とは対照的に車体自体で十分な剛性を確保するA65。正にこのガンとした強さを是非とも記憶してもらいたい。
そして、1970年製のA65Lライトニングがようやく完成した。エンジンの中から車体に至るまで恐らく世界中で最も状態の良い部類だ。流石の私も手元に置いておくべきだったと後悔する・・・そして、新規検査登録を受け試運転の準備をする。「ズッズッズッズッズッズッ・・・ズッウォーーーーーン!・・・」 サウンドは他のブリティシュとは異質で、それでいてバイブレーションは良い意味で強烈だ。
スロットルを開けて走り出すとその感覚の違いが魅力的だ。ショートストロークのストレスない吹け上がり感も素晴らしい。 「ドゥォーーーーーン!・・・んっコンッ・・・ズッウォーーーーーン!・・・んっコンッ・・・」 シフトチェンジシステムは古典的でストロークも長く剛性も低い、速くやろうとするよりも逆に大らかに操作する事がコツだ。
そしてA65の上手な走り方とは「全開走行あるのみ!」だ。タラタラ走るとかトロトロ走るなんぞもっての外!「ドゥォーーーーーン!・・・」 好きなだけスロットルを開けて走るべしっ!
緩い登坂を見つけたら練習してみよう。先ずは「1速2速とスロットル全開で走れっ!」次に、「3速全開したらフライホイールの勢いに意識を移せっ!」 そして、「4速全開!どんどんとフライホイールに勢いをつけろっ!」最後は、「後はハンドルしっかり持って、突っ込まないように注意しやがれっ!」・・・・・こうするとフライホイールの動きが良く分かる。自分勝手にスロットルだけをあおっても駄目だ。素早く徐々に可能な限りフライホイールの回転数を上げて行く亊・・これが出来れば君も一人前のA65乗りだ。
次にコーナーもやってみよう。A65はトライアンフに比べて嫌でも後ろに座る事になる。これが味噌。更に意識してお尻を後ろにずらす・・・コーナーでは終始この位置を意識しよう。要する後輪の真上に座っている感覚で走る事が大事だ。更に頭の位置を下げ、タンクやフットレストを積極的にホールドする。これが出来れば苦手のコーナーリングも好きになれるさ。
「ドゥォーーーーーン!・・・んっコンッ・・・ズッウォーーーーーン!・・・んっコンッ・・・」このように、他の英国車と違いA65は全くの別物。高い剛性を持つエンジンと車体が、性能の良いエンジンのパワーを効率良く路面に伝えてくれる正に 「The British Dynamite!」 次世代を睨み先進的設計を備えた世界をリードすべきモデルのはずだったんだ・・・
そんなA65と旅に出る事は素晴らしい。久し振りに晴れた秋空の下、青い海を求めていつもの丹後半島へとやって来た。
皆さんは一人で旅に出るのだろうか?・・・たまにはひとり、遠くへ行ってみると良い・・・そんな時には海を目指して走ってみると良い・・・綺麗な夕陽を眺めに行こう・・・何処までも夕陽と追いかけっこをしよう・・・この美しい景色を見るだけの事がとっても大切な亊なんだって・・・
都会の交差点を走る事も良いけれど、遠くに行かなきゃ絶対に夕陽には会えないから、やっぱり行くべきなんだ・・・ブリティシュに乗って行く旅ってそんなに行けないから沢山行くべきなんだって・・・
私は今回渾身の力でこのA65を整備した、願わくばずっと幸せに過ごして欲しい。誰よりもオーナーと一緒に走ってもらって・・・誰よりも大事に洗ってもらって・・・誰よりもオイルを替えてもらって・・・それが私の心からの願いなんだ・・・「ありがとうライトニング・・・ここまで残ってくれて・・・」 私はそっとライトニングに頭を下げたんだ・・・ 2017/10/29 布引クラシックス 松枝
そして、季節もすっかり変わった師走、オーナーのUさんが甥っ子さんと一緒に引き取りに来てくれました。甥っ子さんは刀1100に乗ってるとの事。国は違えど同じ旧車乗りとは親近感沸きますね。
店で基本的な筝を説明の後、実際に走ってもらいました。右側に変わるシフトレバーと減速時のシフトダウンのやり方を重点的にアドバイス・・・しかし、どうですか皆さん?初めての英国車とは思えない程イイ感じで走ってますよね。加速の仕方も上手だし、後は減速時のシフトダウンを自分のモノにすれば大丈夫。春には3人で走りに行こうと約束もし、有意義な時間となりましたよ。 2017/12/11 布引クラシックス松枝
参考データー
一般道走行距離 270.6km
高速道路 15.8km
総走行距離 286.4km
ガソリン使用量 11.4L(プレミアムガソリン)
燃費 23.7km/L
燃料タンク容量 9L(2gal.)
試運転コース
Posted by nunobiki_classics at
18:57
│作業完成報告 BSA