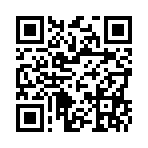2019年12月16日
1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その10
88のボアストロークは66x72.6mmで排気量は497ccだ。だが、この88には650SS用のシリンダーが取り付けられボアが68mmの527ccとなっている・・・
エンジンの性能を上げる場合、最も有効な手段が排気量を上げる事だ。で、それはどちらかと言うとトルクの増大に向く。よってトルクの小さな88には有効だ。
スチール製のHビームなコネクティングロッドは美しい。しかし、一般道を走るTさんにはそっちの方向を極めてはいけない・・・
イグニッションシステムも既に無接点式のボイヤー社のモノに交換されている。これは有効な回転域を上げようとするこのエンジンには当然の選択だ。メカニカルな標準のマグネトー点火装置では回転数が上がるにつれ予定通りの仕事は出来なくなる。レースの世界で使わなければ勝てないと言っても過言じゃない・・・そして、一般道でもその恩恵を受ける事が出来る。古いクルマのトラブルの約半数以上はイグニッション系統もの。調整もメンテナンスも何も要らない。いつ始動しようとしてもトラブルは起こらない・・・それはTさんにとってとっても大切な事なんだ・・・無論ルーカス社製のマグネトーはカッコ良いし素敵だ。私個人のモノならマグネトーで走るさ・・・けれど誰もが忙しい社会人・・・さっと乗って次の日は又仕事なんだろ?・・・どちらが良いとは言っていない。自分の技量に合わせて選べばいい・・・それだけの話なんだ。
これは分解前のプライマリー減速装置の状態でレース用として幅40mmのベルトを使っている。只、500㏄クラスに40mmは結構な容量で、ましてや一般道では逆効果だ。そして、その取り付け方が非常にまずい。重いローターがとんでもなく遠い位置にありクランクシャフト上に殆ど乗っていない。それは発電機の装着を想定していない40mm幅に無理矢理取り付けた格好だからだ。細く長ーいスタッドボルトが弱々しくステーターコイルを支えていて怖くて見てられない・・・
そんな遠い場所の発電装置をぐっと寄せてしっかりとクランクシャフト上に移動しよう!・・・で、グレー色のモノが取り寄せた30mm幅のプーリー、左上のブラケットハウジングにはしっかりとした短く中央部に太さのある1/4インチ径のスタッドボルトを、右下には幾種類かのカラーが並ぶ、こられは布引自家製だ・・・
取り付ける場所の感じはこんなだ・・・
すると、ハウジングがベルトの振れに近すぎてダメだ。フライス盤で慎重に必要な分のみ削り取る・・・
そして、寄せて寄せて詰めて計測して結果この位置になる・・・
ノックピンの位置もあるからどこでも可能な訳じゃないが、これ位詰めれば大丈夫だ・・・
ハウジングも取り付けて完成した図。どうだよ、元の時よりも35mmも中に入れたんだぞっ・・・
こうして危険な位置にあった発電機一式が普通の場所?に納まった。高速で回転する軸上ではモノは遠くなる程暴れる傾向になる。こうしてぐっと締まった筋肉のようにコンパクトになる事は末端が長いクランクシャフトを持つブリティシュには大切なんだな・・・松枝
1975 NORTON COMMANDO 850 Mk3 Roadster プチ報告その6
1965 TRIUMPH T120R プチ報告その4
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その17
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その16
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その15
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その14
1965 TRIUMPH T120R プチ報告その4
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その17
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その16
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その15
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その14
Posted by nunobiki_classics at 21:19
│作業中車両のプチ報告