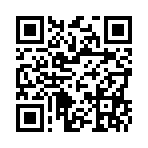2015年06月12日
1971 HONDA CB750K1 整備報告 オーナー 大阪市帝塚山 H様
ある日ゴールドカラーも美しい一台のホンダが送られて来た。10代の頃より遠ざかっていたバイクに再び乗るのだとオーナーからメンテナンスの依頼だ。社会的地位も高い彼のような年齢層では旧車ならではのリスクは歓迎されない。走りに行ったその翌早朝には何事も無かったかのような顔をして職務に就く必要があるからだ。メードインジャパンだからと古い車体を甘く見てはいけない。今回はできるだけオリジナリティーを守りながら、トラブルフリーの車体へと作り変えてみようと思う。
旧車に於けるトラブルの原因のトップは紛れもなく電装系だ。この状況を見て皆さんはどう思う?メインハーネスしかり、スイッチやリレーしかり、50年来交換されずに居るこうした電気系統の傷みを楽観的に見る事は命取りだ。先ずは使えないんだという立ち位置から物事が始まる。
今回はスタンダードの電子部品をそっと箱の中に仕舞い込み現代的なものへとモディファイする。先ずはそれらが正しく着くようにベースプレートをフライス盤でアルミ板から削り出し、必要な穴や長穴の加工をする。手で板を切り出すよりも直角度や位置関係が正確に作れる。
点火系にはフルトランジスター式の点火装置を取り付けよう。トランジスターで増幅されたスパークは低温下でも力強く、無接点式のピックアップ装置は普遍的にそのタイミングを維持する。バッテリーからの電気の供給さえ安定して行えばトラブルを起こす事はない。
付属のローターをフライス加工した後、こうしてピックアップ部分を組み込んだ。これで点火系のトラブルから彼を守れる。もちろんの事劣化したイグニッションコイルにプラグキャップに至るまで新しく交換し、各スイッチの類は全て分解して接点を回復させた。何度も言うが電気とは全て回路になっている。ここはやったけど、あっちはそのままだ・・・なんて話は意味を成さない。全てやり抜く事が必要だ。
先にフライス盤で削り出したアルミのプレートは目立たないように塗装をして元からある穴などを利用してしっかりと取り付けた。右側からフューズボックスにその裏がスーターリレー、左の赤い箱がフルトランジスターの点火装置のコントロールボックス、そして左端にあるのがレギュレータ&レクチファイアー、更にはメインハーネスにイグニッションコイルなどなど…こうした電装系統の中枢部品を全て新しく刷新した。
斜めから見るとこうだ。レギュレーターは熱を発するので空冷のフィンを前方に、イグナイターとの間には断熱材を入れている。標準のフューズボックスはチャーミングだから元の位置に置いた。この時ハーネス等を止めるバンドにもオリジナリティーを守りたい。アルミにコーティングしたこれらは旧車レストアの必須アイテムだ。こうして丁寧に違和感なく取り付ける事は歴史的価値の有る名車をモディファイしてしまう事への礼儀なんだ。
ブレーキ回りも50年来のまま大きな修復を受けていない。リザーブタンクの蓋を開けると既にブレーキフルードは無く、マスターシリンダーからキャリパーの内部にまで腐食が進み完全に使えない状態になっている。
全てのシリンダー面を修復し、シール類を始め必要な部品を交換する。そして塗装の剥げ落ちだキャリパーをサンドブラストした上に塗装する。アルマイトの退色したマスターシリンダーはそのまま使い貴重な状態を踏襲する。
これはホンダ独自のフローティング機構の本体。アルミ製の長いプレートの先にキャリパーが着く。右側には軸が有ってそこを中心に左右に振れる構造だ。だが、古くなると左側の先端がディスクローターに接触しているモノが殆どだ。軸の当りを修正しシムを入れて高さをこうして戻してやる。実際の制動時にはもちろん下がってくるがこの位だと理想的に作動する丁度よい位置だと言える。
最後にブレーキホースやチューブ、曲面を持つ独特のパッドに及ぶまで全てにおいて作業を終えた。そのタッチも当時のままに再現され好感待てるモノとなる。但し、このブレーキは音が出る。こうしたフロートする構造から振動源が多く軽く握ると鳴きが出る。だが、これもホンダCB750オーナーの密かな楽しみなのかも知れない。
次にステアリングに歪みを見つけたので分解する。やはりベアリングのレースが割れステアリングステムは激しく曲がっている。けれど50年来存在しているのだから、こうした事のひとつやふたつ有ってしかるべきだと大きな心で臨むべき。それが旧車を愛する者の心得だ。
状態の良いステムを捜しだし、寸法を確認しネジ山を修正し塗装をする。ここにはステアリングのロックがある。当時のホンダは番号でキーが管理され、当然のようにメインスイッチとは共通したキーになる。しかし、現時点で両者が揃っている車体は少なく、2本のキーを持ち歩く事が常だ。今回は昔のように1本で使えるようにした。
ステムを車体に取り付ける。今回はボールに変えこのテーパーローラーベアリングにモディファイした。200キロを優に超える車体にこそ大変な効力を発揮する。
そしてホイールベアリングを始め各部品を洗浄、交換等を行った後、ブレーキ、ホイール、ステアリングにフロントフォークなどフロント廻りを組み上げる。内容の伴う作業を施した時、おのずと外からでも凛と見える。このフロント廻りに於ける安心感とは相当大切なモノになるんだ。
我が英国車に採用されているアマル社製のキャブレターでは、結構な時間放置しても始動出来る場合が多い。それに対して日本製キャブレターでは数カ月の放置で始動が困難になる。世界一優れたキャブレターではあるがそれが唯一の欠点だ。設計が凝りに凝っていて各通路も狭く酸化物で詰まり易い。そして耐用年数も本来長くない。50年来のいわゆる「国産旧車」に於いて、キャブレターの寿命は大きな問題となっているんだ。
旧車ブームである昨今、何度修理しても直らないと言うケースが後を絶たない。修理に出しても又同じだった…皆さんにも苦い経験があったかと思う。こうした古いキャブレターだは意外な場所に摩耗が起こったり、過去に誰かが穴を広げたり致命的な損傷もあるなど、ありとあらゆる疑いを持つべきだ。
その一例がこれだ。両端がご存知ジェットニードル、スロットル開度に応じて燃料の流量を決める大切な部品だ。そして真ん中のモノがそれに嵌るニードルジェットだ。この両者の隙間で流量が決まる。右側が新品で左側が古いモノ、ジェットの穴が歪になっているのが見えるだろうか?これではまともに燃料を送れない。何時まで経っても交換されずに半世紀 「お客さん…旧車ってこんなもんだよ…」 と言いうお決まりのフレーズに見送られ悔しい想いをして来た光景が目に浮かぶ…
混合比が適切になったエンジンの吹け上がり方は素晴らしい。今までの不調が嘘のようだ。現代の4シリンダーには無い図太く野性的なホンダサウンドにゾクゾクとした感動が湧く、一瞬重いのかと思わせながら力強く拭け上がるエンジンフィーリングはホンダCB750本来の姿だ。
1970年代のバイクではクラッチレバーやスロットルなど人間の操作する箇所には余り神経を使い設計はされていない。このホンダとて同じ。とにかくスロットルが重い。K0では4本のケーブルの合算が、K1では複雑なリンク機構の特性から重い。リターン用のスプリングを各種製作し試してみた。なかなかこれは難しく数種類のもを製作しては具合を見る。引く力と戻す力の妥協点を探り吟味する。試行錯誤した後、スタンダードとは較べものにならない程スムースに開ける事が出来るようになった。
折角完成した時に蒸し返すが聞いて欲しい。私は時代的な価値を考えるからこそ、或いはお金をもらってやるからこそ意地でもこうして再生させる。当然の事だ。しかし、皆さんに於いては余り無理をしない事だ。こうした古いキャブレターを甘く見ちゃいけない。人の命を危険にさらす事もあるからだ。いっそのこと今市販されているCRキャブレターに交換する事の方が安全且つ快適であることは明白な事実だ。その方が安全に楽しく始動からコーナーリングに於いてまで素晴らしい走りを楽しめる。基本的にデリケートなキャブレターとは本来50年間も使えるものじゃないのだと意識を変えてほしいと思う・・・
他にも書き切れない位の作業があって、なんだかんだと言いながら全てを終えた。機能を失っていたブレーキはパッドからマスターシリンダーまで全て完全に修復しこの車体としての制動力を取り戻した。寿命の来ているオリジナルの貴重なキャブレターには出来得る限りの作業を施し軽くスムースに廻せるスロットルと共に快適に走る事ができるようにした。そして、充電装置には近代的な制御機器に改め信頼性を上げる。点火装置にはフルトランジスター式に交換し普遍的な安心感を与えた。数10年振りに走らせる彼の為の準備は整った…
「プッォーーーーーーーードゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ・・・」
エンジンを始動し暖める。フルトランジスタ式の点火装置に適切な混合比率を取り戻したオリジナルの京浜製キャブレター、そのエンジンサウンドは至極健康的だ。4っつの音が和音になって奏でる。只、スタンダードなのにこの4サイレンサーの音は正直でかい!更に野性味溢れる野太いCBサウンドだから更に迫力が増す。聞いていると何だか楽しくなって来てつい笑ってしまった…
例の如く、早速高速道路で市街地を抜ける。適切に配置された5スピードギアのミッションだから加速する仕草には不自然さは無くどんどんと前に走りだす。パワーバンドを嫌でも適切な位置に配するギア比設定は英国車にはない次世代感覚だ。そして写真にある赤いライトはご存知「速度警告灯」!?当時のバイクを知る40~50代世代の典型的な懐かしアイテムだ。赤く光る瞬間に16才に戻れる!あの輝いていた少年の頃に戻れる!何も考えずに只スロットルを開け続けていたあの頃に戻れるんだ!・・・そんな密かなお楽しみアイテムを存分に堪能する心を忘れてはいけないさ・・・。
当時の各メーカーのトップモデルの車重は重く、殆どが200キロを優に超える。このホンダも220~240キロになり、巨大なエンジンがその直接の要因となる。年輩のライダーに於いてはその取回しが少しばかりネックになる。残念な事に10代と較べると筋力は明らかに落ちている。この小さなエンジンガードは格好が悪いと思うかな?下手の証しだと思うかい?しかし私は決してそうは思わない。少し恥ずかしさが有りつつも堂々と付ければ良い。それが大人の趣味と言うものなんだ。
こうした田舎道を走る時「んー・・・コイツを買って良かった・・・」そう思うに違いない。少しの角度でパンクさせ、ひらりひらりと左右に旋回を繰り返す。車体を起こすたびにスロットルを当てて、車体を倒す為に瞬時に戻す・・・この一連の動作から来る幸せ感をもう一度見つめてみよう・・・
「ブォーン・・・ズッズッズッズッズッ・・・ドゥッウォーー――ン・・・」
思い切ってメリハリをつければ更に楽しくなる。それはやっぱりアナログで、求めていたものだと直感する・・・
そして峠道に差し掛かったならこの日一番のハイライトシーンが訪れたと心躍らせなければならない。
「ブォーン・・・ドゥッウォ――――ン・・・ドゥッウォ――――ン・・・」
どうせやるなら昔のように上手に走りたい。先ず思っている倍近い勢いでコーナーに入ってみよう。そんな遅い速度ではコーナーリングは始まらない・・・思い切って突っ込んだと同時にフロントフォークを沈めるようにすーっと前後のブレーキを操作しよう。フットレストに体重を載せ車体をホールドし脇を大きく開けてみるんだ・・・更にコーナーの出口が見えたなら遠くを見つめて美しく大端にスロットルを開けてみろっ!・・・
次のコーナーで再び車体が倒れたなら意識はずっとフットレストと目線に集中させてみるんだっ!
「ブォーン・・・ドゥッウォ――――ン・・・ドゥッウォ――――ン・・・」
そしてこの時最も大切な事は「クランクシャフトの存在感」だ。直線から車体をパンクさせる時、あの長いクランクシャフトを振り廻す感覚を体に染みつけて欲しい。「ズッドーンと加速して閉じて、いざっクランクシャフトを倒し込む!ズッドーンと加速して閉じて、いざっクランクシャフトを倒し込む!」速度を調整するのは何もブレーキだけじゃない。こうしたスロットル操作はこの時最大の速度調整装置なんだ。メリハリを忘れるなっ!はっきりと操作しろっ!もっと本気でやってみるんだっ!・・・必ず必ずやこの時、君のCB750は快楽の世界へと誘ってくれるはずだっ!
ここは三方五湖。関西圏の方なら大体の位置関係は分かる。ここまでの走行距離は約200キロ。寒い寒いと言いながら何事もなかったかのように走ってくれた。サスペンションはお世辞にも良好とは言い難く強い衝撃が直接伝わる1970年代そのままのものだ。なので現行車よりも疲労は進むもの。「あ~走ったなー・・・」腕は疲れ、腰は痛い、全身に疲労感が蔓延する・・・でもそれが1970年代のバイクだったじゃないか?・・・
「ブォ――――ン・・・ドゥッドゥッドゥッドゥッ・・・ドゥッウォ――――ン・・・」
真っ直ぐな道を風を受けて走る時、そのホンダサウンドは心に残る。風の音と4サイレンサーから奏でるホンダミュージックはひとえに快感だ。跨って走らせている事自体が素晴らしくて心に浸みて来る。名車とはそういうモノだと改めて思うんだ・・・。
こうして遠い地にひとりで走りに行く事は大人のロマンだ。昔憧れた名車を駆り瞬時にして目的地に辿りつく。いろいろな事経験した・・・沢山の事を見て来た・・・一通り人生を経験して来たからこそ今は只走りたい・・・。理屈なんてないさ。理由なんかあるものか。只々昔のように走りたい・・・それだけなんだ。
皆さんも10代の頃、きっとバイクに乗っていたに違いない。憧れの大型免許に諦めつつもこうしたナナハンに皆が憧れを抱いていたはずだ。君達は今一体何才なんだい?屋根のついた高級車もそりゃいいさ。だけれどもそうじゃない。もう一度ハンドルを握ってみるべきじゃないのかい?風を受けて涙を流して鼻水を垂らして走ってみようじゃないか?その時に、その時にこの「CB750」は必ず夢を叶えてくれる!1968年にデビューし世界のモーターサイクル界を根底から覆した名車中の名車。全ての英国車を墓場へと葬り去った若きホンダマンの夢のマシン。世界中から認められたこの4シリンダーは強烈な存在感を示す。 「HONDA CB750Four」 それは今指をくわえて見ている君達が最後に乗るべきマシンなんだっ!
そして彼がオーナーのH氏だ。彼は16才直ぐに免許を取りヤマハの2ストロークマシン「RD350」で走りだした。とにかくどんな道であろうが彼はスロットル全開で走る。巷では「伝説の全開ライダー」として知られた。直線だろうがコーナーであろうがとにかくスロットルを緩めない。信号が青に変わる途端にスロットル全開!交差点を曲がれば全開!ブラインドの峠道でも全て全開で、まるで本能だけで生きる野獣のようだった。当然ながら危ない目にも多々遭う事になる。足から血が吹き出ていても走り続けた。骨折しようがお構いなし。本当に速くて凄い奴だった。そして、同い年の私はカワサキのマッハで彼に対抗した。「ヤマハRDとカワサキのマッハ」彼と私はいつも二人で走っていた。ホームグラウンドの六甲の山々を段差のひとつまでも知り尽くし走り続けた40年前・・・それは生涯忘れる事の出来ない最も輝いていた青春の一ページだったんだ・・・
そうして大人になった彼の選んだ「HONDA CB750」。2ストロークマシンではないけれど、きっとこれからの人生の一ページに充実した記録を残してくれるはずだ。難しく手間のかかる英国車よりもずつと信頼性が高い事は紛れもない事実だ。但し、何もせずに古いバイクは走らない。彼のように真剣に愛車を正しいモノにしたいと言う心づもりがなければ不幸な事になる。電装系やキャブレターなど耐久性の低い箇所には徹底した作業が不可欠だ。その上で手に入れたなら、存分に第二のバイク人生を楽しめる。機械を正しく機能させる事にメーカーの国境など無いって事を肝に銘じなきゃならないって訳なんだ・・・
試運転の詳細
一般道の走行距離 222km
高速道路の走行距離 179km
総走行距離 401km
使用ガソリン 17.43L(レギュラー)
燃費 23.0km/L
1986 DUCATI 750F1-3 一般修理作業報告 西宮市T様
1955 BMW R50 神戸市 Y様 車検整備
1989 DUCATI 900SS プチ修理しました。
1972 HONDA CB750K1 新たなオーナーの下へ!兵庫県N様
1980 HONDA CB750FA エンジン修理作業報告
1986 DUCATI 750F1 修理報告
1955 BMW R50 神戸市 Y様 車検整備
1989 DUCATI 900SS プチ修理しました。
1972 HONDA CB750K1 新たなオーナーの下へ!兵庫県N様
1980 HONDA CB750FA エンジン修理作業報告
1986 DUCATI 750F1 修理報告
Posted by nunobiki_classics at 21:42
│作業完成報告 その他