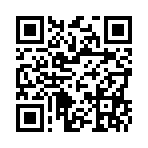2020年02月13日
1965 TRIUMPH T120R プチ報告その4
Aさんのボンネヴィル、車体の分解作業していますよ・・・
ホイール外して、フロントフォーク外して、車体を洗浄して・・・
スイングアームに、プロップスタンドに、ブレーキトルクステイも取り外しました。
1965年製のブリティシュではこのような油汚れがびっしりとこびりついているって、これ普通よりも全然マシな方なんです。
ステアリングのベアリングはスーッと軽やかな作動でなければなりません。こうした古いベアリングでは、使えないモノがほとんど・・・しかしこれ、グリスの硬化だけでボールやレースには摩耗なし!イイ感じです。
エンジンも大方の部品を取り外し・・・
降ろしましたよ・・・
では、ご報告 優良編です。
・エンジンは一度も降ろされた跡がない(変にいじられていない事は大切)。
・各スタッドボルトやナットにワッシャーなど新車時のモノ(上質な車両が作れる)。
・当時の亜鉛メッキの残るボルト類が嬉しい(同じく)。
・ステアリングは古いグリスの硬化のみで状態良好(これも嬉しい)。
・フロントフォークは何度か分解された後があるもののそれなり(普通より断然良い)。
・スイングアームは、摩耗がなく良好な状態(よしよし…)。
次に、ご報告 悪い状態編・・・
・フレームの塗装に手塗りの修復跡が多々ある(質感悪い)。
・シートレール部分に穴を開けた跡がある(シーシーバーの跡)。
・センタースタンド、プロップスタンドに曲がりや欠損がある(トラでは普通の事)。
そして、今後の方向性は・・・
・シートレールやスタンド類に溶接修理が必要なのと、手塗りの跡を考慮しフレームなどブラック系の塗装を決行する!(予算心配納まる?)
・エンジンは至極良好なので普通に進めて行ける(好材料、超嬉しい)。
次は、ブラック系の塗装パーツの準備作業を経て塗装を行います!では・・・松枝
Posted by nunobiki_classics at
22:50
│作業中車両のプチ報告
2020年02月05日
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その17
こうした世界でのぺトロールタンクの取付方は極めてテキトウだ。この88はその中でもトップクラスのいい加減さ、ラバーを巻いて「はい、おしまい…」 とてもじゃないがこんなんじゃ乗れない。
触ればよれよれと動くタンクを可能な限り改善しようと思う。で、前方にはレース用のラバーを配し、なんの取っ掛かりもない後方には幅の広い受けを作る事にした・・・
先ず、メインフレームにメンバーを溶接する・・・
別に作ったブラケットを載せる・・・
で、位置決めの後中央部分を切り取り、タンクとの接触面には10mm程度のラバーを貼る、こうすれば軽くなるし並行度も決まり、更に将来の変更にも対応し易い。そしてここのポイントはブリティシュのボルト&ナットだ・・・
で、一枚のアルミ板を曲げて巻いていただけの留め具は、分割しフライス加工による長穴加工を施し調整機能を与えた。
これでやっとこの88のタンクもぐらぐらと動くような事はなくなった。固着していたぺトロールタップやホースも交換し見違えるほどイイ感じになった。
一般道を走るにはスタンドは大切な存在だ。角度に合わせて底面を削られたこれはどう見ても削り過ぎ、ハンマーで軽く叩いてみればこのありさままだ・・・
厚みのある鉄板をおおよその形に切り取り溶接していく・・・
状況にもよるが、肉盛りしていくよりも、こうする方が結果は良くなる・・・
塗装をして・・・
誰が見ても恥ずかしくない姿に戻った・・・
この88にはリアの隙間が45ミリ程度しかない。リジットモデルじゃあるまいしスイングアームモデルでは非常識だ。そして、軽量化の為とアルミ製のマッドガードがついているが、その辺りも普通に走れるようにしなけりゃならない・・・
一般道では是非スチール製にして欲しいものの、もう使っているんだから仕方がない。上に載せているトライアンフ用のライセンスプレートの重量がアルミ製のマッドガードに振動と共に容赦なくのしかかる・・・
せめてその負荷をシートレール本体に載せてやらなきゃ・・・
数か月の寿命のアルミ製を少しでももたせると共に、シートレールの固定穴を加工しホイールトラベルも十分なモノとした。

そして、この他にも本当にくたびれる程多数の作業を行いその山場は超えた・・・そして継続検査も受けた。後は試運転に出掛けようと思う・・・
Posted by nunobiki_classics at
20:38
│作業中車両のプチ報告
2020年02月03日
1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その16
古いモーターサイクルの多くは、こうしてエンジンとギアボックスが独立していてそれをチェーンで連結する。そして、今日のサンデーレースなどでは強化繊維の織り込まれたベルト駆動が広く利用されている。
この88は、スタンダードのカバー類が取り外されたいわゆるオープンプライマリーだ。
見ると、センターナットにはワイヤーロックが複数かけられ、締めても締めても続くナットの緩みに、ずっと悩まされていたようだ・・・
で、ここには走行中のスロットルの開閉により激しい応力が集中する。なので、大きなスプライン加工が施されている・・・実は、元々ドミ系のここにはウイークポイントがあるんだ・・・
スプラインを良く見てみよう・・・ヘコミとデッパリの幅が違う事が分かるだろうか?・・・これは、メインシャフト側を保護しクラッチセンター側に負担が多く分配されている格好だがこれがドミ系の弱点となる・・・次にその奥を見ると、どん突きになっているね?要するにナットを締める事によりこのどん突きの面とメインシャフトの端面を締結する格好だ。だが、一点に応力が集中するこのやり方もスプライン同様弱点となる。
で、コマンド系ではそのどん突きを廃止し軸に対してフリーとした。そして、ギアボックス側にロケーションサークリップとカラーを使った固定場所を設け応力を分散させる。更に、スプラインの幅を同じとし、それ以降、ドミ系の弱点である編摩耗と緩みは解消したと言う訳なんだ。なので、この部分のドミ系とコマンド系には互換性はない。
これはこの88だ。おかしいと思わないかい?・・・驚いた事に互換性のないドミ系とコマンド系を合わせてしまっている・・・これではいくらナットを締めても緩み続けて当然の状態だ。
この写真を見て、怖くならないかい?・・・長いメインシャフトの先端に片手で持てない位の重いクラッチが載っている。更にスロットルの開閉で激しく前後に振られる、それが走行中に高速回転するんだぞ・・・「こんなに危険な状態なんだ・・・」そう思ってしかるべきだ。
最近では、一般の素人さんでも手軽にバイクの整備をやるようになったとか・・・こんな時代だからユーチューブを見れば即整備士クラスになれるらしい・・・インターネットで調べれば即ベテランの整備士になれるらしい・・・だがな、この重いクラッチがサーキットコースで飛んで行ったなら・・・路上の通行者に当たってしまったなら・・・一体どうなると思う?・・・サンデーメカニックの皆さん、やっていい事と悪い事があると明日から肝に銘じて欲しい。
そして、製造元のボブニュービーレーシング社に連絡をとると、これは当社の初期のモデルだから危険だと新調する事に・・・届いたモノを見ていると「イギリスっていいよなぁ…モノがいいよなぁ…」 モータースポーツの聖地イギリスってやっぱりいいんだよなぁっと思う訳。 ボブニュービーレーシングは→コチラ
古いブリティシュのクラッチとは比較しようがない位に出来が悪い。だから、こうした精度の高いモノを入れることによって安全性がすこぶる高まる。他人事ではないと皆さんにも認知してもらいたい。
皆さんはたかがクラッチだと思うかもしれない。しかし、エンジンが5千回転廻ればここはおおよそ2.5千回転廻る。その回転の勢いとはタコメーター如きのモノじゃない。だから私はこうしたオープンプライマリーなど大反対だ。万が一、取り返しのつかない事になったならどうするんだ。
けれど、今回は修理の依頼だからオーナーの意向を曲げてまで仕事をする事もそれにそぐわない。しかし、何れの日にか「カバーつけましたよ…」 Tさんがそう言ってくれる事を期待したい・・・
Posted by nunobiki_classics at
01:02
│作業中車両のプチ報告