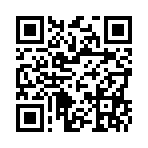2012年11月10日
クラシックなものが大好きなあの人のコマンド その1
クラシックなものが大好きなナイスミドルのオーナー。
モノにこだわりを持つ感性豊かな彼の為に、精一杯の仕事をしてみた。

これは、1972年にデリバリーが始まった当時のノートンコマンド プロダクションレーサー。
皆さんご存じのイタリアはドゥカティのワークスレーサーと双璧をなしたブリティッシュの誇る名機だ。
ノートンマンクスの後継機と言えば分かるだろう。
1971年からスラクストンの小さな専用工場で製作を開始した競技車両。
その台数は100台強と言われてはいるが、実際には不明というのが正しい。
これは、初期のもので後期のものとサイレンサーやオイルタンクなどに違いがある。
当時も高価であったノートンの、更にその憧れとしてマニアの垂涎の的となった。
今回のオーナーは、そんなノートンコマンド プロダクションレーサーに強い憧れをもつ素敵な男性。
もとは大学のラグビー部で腕を鳴らし、今は古いモーターサイクルをこよなく愛している。
彼がコマンドを走らせる時が来るまで、皆さんと共に見て行きたいと思いますよ.....

神戸税関で、いつものように通関手続きを終え、こうして私の愛車シボレーK1500で店に持ち帰った。
開梱する時はいつも、胸がときめくんだ。

これが、神戸港に到着し始めて店に降ろした時の彼のコマンド。
1971年製のロードスターマークⅡだ。
フロントのドラムブレーキと、シルバーのバレルが粋なモデルだ。
今回の車両は、程度も素晴らしく良く優等生だ。
このままのロードスターで仕上げて乗るのが良いと彼に勧めた。
しかし.....
「僕は、プロダクションレーサーで走りたいんです!」
「ロードスターも味があるよ....」
「いえっ、プロダクションレーサーのスタイルとポジションが最高に良いんです!!」
彼は隕石より固い頑固者、私の話に耳も貸さない。
しかし、そんなこだわり抜いた心意気が今の時代に嬉しいじゃないか!
そして、その日からプロダクションレーサー製作への道が始まった.....

分解していくと当初の見解通りモノが良い。
フレームから何から余計な仕事がされていない。
古いこうしたクラシックモーターサイクルでは、いろんな者がいろいろとやってくれる。
的を外した作業を随分としてくれるものだ。しかし、こいつは良い。
これから一生所有していく車両としてベストな選択だった。

そうは言っても、今時のバイクじゃない。このまま洗車して乗ろうなんてモノを知らなさ過ぎる。
造られてから41年。このエンジンの基本設計から63年の月日が経つ。
各部をくまなく調べ上げる事は、至極当然の事だ。

ギアボックスも、プライマリーチェーンケースも、全て調べる。
開けて行くとおおよそ、どんな状況で使われて来たか分かる。
やはり、こいつは良い部類だ....

ギアボックスのケースごとエンジンマウント一式を降ろした。
スイングアームや、マウントのラバーもまとめて外す。
ここは、コマンドの大切な部分。しっかりと仕事をするべき箇所だ。
そして、車両の各部の状態、彼の希望と性格、最終的な予算。
これらを合わせて、彼のコマンドの最終的な指針を決めた。
・この状態であれば、この車体の経歴を大切に残すべきだ。
・当時のプロダクションレーサーの基本スタイルと味を再現しよう。
・品の良い、的を得た、質の高いものにするべきだ。
こうして彼のプロダクションレーサーレプリカへの道が始まった.....

早速エンジンから作業に取り掛かる。
ケースを割り、洗浄、点検、仕上げの済んだクランクシャフトだ。
三者を締結する疲労の進んだ炭素鋼のボルトやナットも新しいモノとしている。
コネクティングロッドの嵌るジャーナル部は、エンジンの性能を決める重要な部分。
今回は幸運にも軽いラッピングで処理できた。
スタンダードのサイズで抑えたと言う事は、後世に残すべき価値ある車両には有益な事なんだ。

そこに嵌るのが、このコネクティングロッドのシェル。皆さんの言うメタルだ。
これは新車時のもので、サイズは当然スタンダード。
表面処理されるホワイトメタルに変色はあるものの、焼き付きも無く良い管理がされていたことが分かる。
これら新しいシェルもワンセットごとにクリアランスを測りベストな位置を捜した。

クランクシャフトの振れ。これは大切だ。当然無いに越した事はない。
しかし、現実にはそうはいかない。振れが大き過ぎて使えないものもある。
このクランクシャフトは、私の経験するモノの中で最良の部類に仕上げた。
内も外もほぼゼロに抑えた。この程度のダイヤルゲージで測る上で、これ以上の結果はない。
この事が、それでなくても強大な振動を発するコマンドにとって大切な事になるんだ。

そのクランクシャフトをケースに収めた。
支えるベアリングは、強度充分なローラータイプを組み込んでいる。
今回のエンジンの答えはここで決まっている。走らせる時が待ち遠しい.....
カムシャフトには、低速も粘り、上まで廻る私の愛車と同じものを使用した。
バルブのリフト量もかなり増えるので、ピストンヘッドとの干渉には注意する。
詰め込むガスの量が相当多くなるので燃料の消費が気になるところだ。
しかし、私の愛車では良い時で28km/L 悪い時にでも25km/Lは確保している。
全ての面で、公道で走るプロダクションレーサーに最もふさわしいものとした。

交換したピストンがこれだ。
先の写真にもある当時のスタンダードのピストンでは、スタイル的に白煙や熱ダレが顕著に出る。
それに加え、シリンダーの摩耗の度合いからワンサイズ上げることにした。
そして、ここにあるピストンリング。これを侮ってはいけない。
例えば、どんな高価なピストンでもこのリングが予定通りの仕事をしなければまともに走れない。
更に、各部の隙間を逐一確認し修正する。
新品であろうが、再使用であろうが、このリングの動きを妨げている要素は取り除く。メカとしての鉄則だ。
只の輪っかだと思うこと無かれ、これがエンジンの生命線と言っても過言じゃないんだ。

いつも言ってるシリンダヘッドにあるバルブ廻りの大切さ。手の抜けないバルブの密着性の確保。
今回も、バルブ、ガイド、スプリングを交換した。バルブシートのカットや擦り合わせも当然の事。
エンジンの中でも疲労が最も早いバルブガイドの摩耗。
今回のガイドには、耐摩耗性の高い鋳鉄製を選んだ。
オーナーの使用状況から熱的な懸念より、安定した性能を長く維持出来ることを目的とした。
また、プロダクションレーサーの標準的な圧縮比は高く、公道で使用する設定ではない。
カムシャフトと合わせバランスのとれた圧縮比とした。
高い馬力を求めるだけでは良いマシンはできない。
ナンバープレートのついた車両が、公道上で最高の喜びを味わえるようにする事。
スロットルを捻るオーナーに、質の高い感動を与える事。それが今回の狙いだからだ。
また、3本のスタッドボルトに始まる、イギリス製のボルト類。
これらをあるべきところにあるべき姿で修復するのが私のスタイル。
たった一本のボルトに手をぬくと、最後のつけはとてつもなく大きなモノになる。
ネジ山の壊れたシリンダーヘッドでは、良い仕事も何もない訳だ。

繰り返すが、このスタッドボルトとナットに厚みのある小径のワッシャーがコマンドの正規のものだ。
年式によって英国、米国双方の規格が混ざる。どちらにしてもこうした景色が質の高いエンジンを生むんだ。

これも同じく正規のシリンダーヘッドボルトとワッシャーだ。
何でもないようなモノと思われがちだが、締め付ける力をしっかりと伝えてくれる。
私にとっては大切なこだわりのパーツ達なんだ。
そして、私はチャンピオンのスパークプラグを取り付ける。
文字と全体のスタイルの美しさが何とも言えず好きなんだ。
プラグのキャップを閉めてしまえば、それは全く見えなくなってしまう。
けれどそれでいい。モノへのこだわりとはそういうものなのさ.....

そして、ボーリングを終えたシリンダーを組み合わせた。
ホーニングの筋がオイルを捕えているが良く見える。
この美しく輝く銅製のガスケットもクラシックカーを支える小道具と言える。
現代でこれを使うのは、精々四輪車で高度なチューニングを受けた高性能エンジン位だ。
コマンドでは、今と同様のファイバー製のガスケットも選べる。
けれども、私は頑なにこれを使う。
れっきとした理由は別にあるのだが、狭い隙間から見える僅かな景色もクラシックモーターサイクルの粋なんだと考えるからだ。

ヘッドを載せる前に、こうしてイグニッションのタイミングをとっておく。
今回のコマンドには無接点式のボイヤー製点火装置を組み込む。
無反応的なボソボソ感が楽しい機械式の点火装置の魅力を誰よりも私が知っている。
クラシックカーの世界では機械式の点火装置にこだわるべきとも思う。
しかし、プロであるからこそ、そこに執着してはいけない。
頭にあるのはオーナーに適したものを提供する事。オーナーの夢を叶える事。
社会的地位のある忙しい今の彼にはそれがベストな選択なんだ.....。

これが、彼のギアだ。見ての通り、4スピードギアとなる。
上がメインシャフト側、下がレイシャフト側となる。
しっかりとした堅実な造りは、ご存じAMC社によるもの。
コマンドが最後まで使い続けた完成度の高い名品だ。

各種のベアリングやプッシュを交換して、歯の当りに異常が無いかも良く点検する。
届いた新品の消耗部品がそのまま使えるなんて今のメードインジャパンじゃないんだ。
寸法を確認して、すり合わせをして、その動きをも仕上げる必要がある。
ギアボックスにも慣らし運転が必要だと皆さんは理解できるかな?
幾ら分解しましたと言っても、開けで閉めるだけなら誰にでも出来る。
一見単純な構造に見えるけれど、やるべき仕事は多いんだ。
そうして全ての状態に納得した後、ケースに納めた。
少し余談かもしれないが、皆さんもこうしたギアボックスの事を知って欲しいと思う。
当たり前についているギアだけど、そう簡単なものじゃない。
こうした高い負荷に耐え得るものを造り上げると言う事は、皆さんが考えている程容易い事ではない。
設計から、素材から、製造まで、一貫して高い技術が必要だ。
特に製造の過程では、幾つもの工程があって、ちょっとやそっとじゃ出来上がらない。
切削や、研磨や、焼き入れなどの行程が山ほどあって、やっとの思いで出来上がる。
「すっげーなー!」
場数を踏んだ者には、ドキドキするくらいの景色に映ってしかるべきモノなんだ。
だからこそ、皆さんがギアを変えるシフトの操作では、丁寧な操作をするんだと私はいつも言っている。
価値あるものには、価値ある扱い方をする。クラシックカーを愛する皆さんの持つべき人格がそこにある。

かと思えば、いい加減なところもある。下の三つあるラバー製のいわゆるOリング。
これは、始動するスターターレバーのシャフトとシフトシャフトのものだ。
これなんかは、設計がまずく、暫くするとオイルが滲んでしまう。
言わばこの世界の誰もが知っているAMC製ギアボックスの常識だ。
本体のギア一式では感銘する程の仕事をしても、アウターカバーごときには大した配慮もない。
精力的に設計を変更すれば済む話と現代から見ればそうなるが、絶対に変えない。
伝統を、その時代の証を、後世に伝えて行くという絶対的な信念。それが英国製品の粋なんだ。
だから英国車は面白い。メードインイングランド万歳!!と私は言いたいんだな。

そして、こちらがプライマリーチェーンケースの内部だ。
オーナーの要望とを合わせて、今回はベルトキットを取り付けた。
科学繊維の織り込まれたラバー製のコグベルトにアロイ製のプーリーの組み合わせた。
たまに耳にする事に手入れが楽だと言う話を聞く。
しかし、メンテナンスフリーになるなどと勘違いも甚だしい。
本来ウエット状態で使うべきクラッチディスクをドライで使うのだから頻繁に清掃や点検が必要だ。
スチールのクラッチハウジングがアロイ製になってオイルもないのだから摩耗も急速に進む。
本来走行毎に手入れをするレース用部品だと言えば理解されよう。
年間の走行距離が延びる使い方ならば、スタンダードなウエットのものが適している。
クラッチケープルも含めて、定期的にメンテナンスを受けてほしい。
また、左側にある丸い発電用のステーターコイル。
本来の容量から40%程度発電能力の高いモノを取り付けた。
交換した点火装置を含めて充分な容量を確保している。

そして、完成したエンジン本体とギアボックスを車体に載せた。
何時の時にも、こうして苦労をした後、エンジンが完成する事は嬉しい。
一台一台その不具合にも違いがあって、施す作業もいろいろだ。
現代のコンピューター製の機械なら、もう少し効率よく仕事が進む。
言ってはいけない事だけれど、手間も時間も掛かるモノ。
それだけに、全てのエンジンの仕事を憶えている。
あの人のコマンドはこうだったな。この人のトラは、こうだったよ。
ひとつひとつのエンジンに、声を掛けてやりたい位の気になる私は、少しおかしいのかもしれない。
このエンジンのスターターレバーを踏み込むそのオーナーの為に、もうひと仕事する必要がある.....
布引クラシックス 松枝
モノにこだわりを持つ感性豊かな彼の為に、精一杯の仕事をしてみた。

これは、1972年にデリバリーが始まった当時のノートンコマンド プロダクションレーサー。
皆さんご存じのイタリアはドゥカティのワークスレーサーと双璧をなしたブリティッシュの誇る名機だ。
ノートンマンクスの後継機と言えば分かるだろう。
1971年からスラクストンの小さな専用工場で製作を開始した競技車両。
その台数は100台強と言われてはいるが、実際には不明というのが正しい。
これは、初期のもので後期のものとサイレンサーやオイルタンクなどに違いがある。
当時も高価であったノートンの、更にその憧れとしてマニアの垂涎の的となった。
今回のオーナーは、そんなノートンコマンド プロダクションレーサーに強い憧れをもつ素敵な男性。
もとは大学のラグビー部で腕を鳴らし、今は古いモーターサイクルをこよなく愛している。
彼がコマンドを走らせる時が来るまで、皆さんと共に見て行きたいと思いますよ.....
神戸税関で、いつものように通関手続きを終え、こうして私の愛車シボレーK1500で店に持ち帰った。
開梱する時はいつも、胸がときめくんだ。
これが、神戸港に到着し始めて店に降ろした時の彼のコマンド。
1971年製のロードスターマークⅡだ。
フロントのドラムブレーキと、シルバーのバレルが粋なモデルだ。
今回の車両は、程度も素晴らしく良く優等生だ。
このままのロードスターで仕上げて乗るのが良いと彼に勧めた。
しかし.....
「僕は、プロダクションレーサーで走りたいんです!」
「ロードスターも味があるよ....」
「いえっ、プロダクションレーサーのスタイルとポジションが最高に良いんです!!」
彼は隕石より固い頑固者、私の話に耳も貸さない。
しかし、そんなこだわり抜いた心意気が今の時代に嬉しいじゃないか!
そして、その日からプロダクションレーサー製作への道が始まった.....
分解していくと当初の見解通りモノが良い。
フレームから何から余計な仕事がされていない。
古いこうしたクラシックモーターサイクルでは、いろんな者がいろいろとやってくれる。
的を外した作業を随分としてくれるものだ。しかし、こいつは良い。
これから一生所有していく車両としてベストな選択だった。
そうは言っても、今時のバイクじゃない。このまま洗車して乗ろうなんてモノを知らなさ過ぎる。
造られてから41年。このエンジンの基本設計から63年の月日が経つ。
各部をくまなく調べ上げる事は、至極当然の事だ。
ギアボックスも、プライマリーチェーンケースも、全て調べる。
開けて行くとおおよそ、どんな状況で使われて来たか分かる。
やはり、こいつは良い部類だ....
ギアボックスのケースごとエンジンマウント一式を降ろした。
スイングアームや、マウントのラバーもまとめて外す。
ここは、コマンドの大切な部分。しっかりと仕事をするべき箇所だ。
そして、車両の各部の状態、彼の希望と性格、最終的な予算。
これらを合わせて、彼のコマンドの最終的な指針を決めた。
・この状態であれば、この車体の経歴を大切に残すべきだ。
・当時のプロダクションレーサーの基本スタイルと味を再現しよう。
・品の良い、的を得た、質の高いものにするべきだ。
こうして彼のプロダクションレーサーレプリカへの道が始まった.....
早速エンジンから作業に取り掛かる。
ケースを割り、洗浄、点検、仕上げの済んだクランクシャフトだ。
三者を締結する疲労の進んだ炭素鋼のボルトやナットも新しいモノとしている。
コネクティングロッドの嵌るジャーナル部は、エンジンの性能を決める重要な部分。
今回は幸運にも軽いラッピングで処理できた。
スタンダードのサイズで抑えたと言う事は、後世に残すべき価値ある車両には有益な事なんだ。
そこに嵌るのが、このコネクティングロッドのシェル。皆さんの言うメタルだ。
これは新車時のもので、サイズは当然スタンダード。
表面処理されるホワイトメタルに変色はあるものの、焼き付きも無く良い管理がされていたことが分かる。
これら新しいシェルもワンセットごとにクリアランスを測りベストな位置を捜した。
クランクシャフトの振れ。これは大切だ。当然無いに越した事はない。
しかし、現実にはそうはいかない。振れが大き過ぎて使えないものもある。
このクランクシャフトは、私の経験するモノの中で最良の部類に仕上げた。
内も外もほぼゼロに抑えた。この程度のダイヤルゲージで測る上で、これ以上の結果はない。
この事が、それでなくても強大な振動を発するコマンドにとって大切な事になるんだ。
そのクランクシャフトをケースに収めた。
支えるベアリングは、強度充分なローラータイプを組み込んでいる。
今回のエンジンの答えはここで決まっている。走らせる時が待ち遠しい.....
カムシャフトには、低速も粘り、上まで廻る私の愛車と同じものを使用した。
バルブのリフト量もかなり増えるので、ピストンヘッドとの干渉には注意する。
詰め込むガスの量が相当多くなるので燃料の消費が気になるところだ。
しかし、私の愛車では良い時で28km/L 悪い時にでも25km/Lは確保している。
全ての面で、公道で走るプロダクションレーサーに最もふさわしいものとした。
交換したピストンがこれだ。
先の写真にもある当時のスタンダードのピストンでは、スタイル的に白煙や熱ダレが顕著に出る。
それに加え、シリンダーの摩耗の度合いからワンサイズ上げることにした。
そして、ここにあるピストンリング。これを侮ってはいけない。
例えば、どんな高価なピストンでもこのリングが予定通りの仕事をしなければまともに走れない。
更に、各部の隙間を逐一確認し修正する。
新品であろうが、再使用であろうが、このリングの動きを妨げている要素は取り除く。メカとしての鉄則だ。
只の輪っかだと思うこと無かれ、これがエンジンの生命線と言っても過言じゃないんだ。
いつも言ってるシリンダヘッドにあるバルブ廻りの大切さ。手の抜けないバルブの密着性の確保。
今回も、バルブ、ガイド、スプリングを交換した。バルブシートのカットや擦り合わせも当然の事。
エンジンの中でも疲労が最も早いバルブガイドの摩耗。
今回のガイドには、耐摩耗性の高い鋳鉄製を選んだ。
オーナーの使用状況から熱的な懸念より、安定した性能を長く維持出来ることを目的とした。
また、プロダクションレーサーの標準的な圧縮比は高く、公道で使用する設定ではない。
カムシャフトと合わせバランスのとれた圧縮比とした。
高い馬力を求めるだけでは良いマシンはできない。
ナンバープレートのついた車両が、公道上で最高の喜びを味わえるようにする事。
スロットルを捻るオーナーに、質の高い感動を与える事。それが今回の狙いだからだ。
また、3本のスタッドボルトに始まる、イギリス製のボルト類。
これらをあるべきところにあるべき姿で修復するのが私のスタイル。
たった一本のボルトに手をぬくと、最後のつけはとてつもなく大きなモノになる。
ネジ山の壊れたシリンダーヘッドでは、良い仕事も何もない訳だ。
繰り返すが、このスタッドボルトとナットに厚みのある小径のワッシャーがコマンドの正規のものだ。
年式によって英国、米国双方の規格が混ざる。どちらにしてもこうした景色が質の高いエンジンを生むんだ。
これも同じく正規のシリンダーヘッドボルトとワッシャーだ。
何でもないようなモノと思われがちだが、締め付ける力をしっかりと伝えてくれる。
私にとっては大切なこだわりのパーツ達なんだ。
そして、私はチャンピオンのスパークプラグを取り付ける。
文字と全体のスタイルの美しさが何とも言えず好きなんだ。
プラグのキャップを閉めてしまえば、それは全く見えなくなってしまう。
けれどそれでいい。モノへのこだわりとはそういうものなのさ.....
そして、ボーリングを終えたシリンダーを組み合わせた。
ホーニングの筋がオイルを捕えているが良く見える。
この美しく輝く銅製のガスケットもクラシックカーを支える小道具と言える。
現代でこれを使うのは、精々四輪車で高度なチューニングを受けた高性能エンジン位だ。
コマンドでは、今と同様のファイバー製のガスケットも選べる。
けれども、私は頑なにこれを使う。
れっきとした理由は別にあるのだが、狭い隙間から見える僅かな景色もクラシックモーターサイクルの粋なんだと考えるからだ。
ヘッドを載せる前に、こうしてイグニッションのタイミングをとっておく。
今回のコマンドには無接点式のボイヤー製点火装置を組み込む。
無反応的なボソボソ感が楽しい機械式の点火装置の魅力を誰よりも私が知っている。
クラシックカーの世界では機械式の点火装置にこだわるべきとも思う。
しかし、プロであるからこそ、そこに執着してはいけない。
頭にあるのはオーナーに適したものを提供する事。オーナーの夢を叶える事。
社会的地位のある忙しい今の彼にはそれがベストな選択なんだ.....。
これが、彼のギアだ。見ての通り、4スピードギアとなる。
上がメインシャフト側、下がレイシャフト側となる。
しっかりとした堅実な造りは、ご存じAMC社によるもの。
コマンドが最後まで使い続けた完成度の高い名品だ。
各種のベアリングやプッシュを交換して、歯の当りに異常が無いかも良く点検する。
届いた新品の消耗部品がそのまま使えるなんて今のメードインジャパンじゃないんだ。
寸法を確認して、すり合わせをして、その動きをも仕上げる必要がある。
ギアボックスにも慣らし運転が必要だと皆さんは理解できるかな?
幾ら分解しましたと言っても、開けで閉めるだけなら誰にでも出来る。
一見単純な構造に見えるけれど、やるべき仕事は多いんだ。
そうして全ての状態に納得した後、ケースに納めた。
少し余談かもしれないが、皆さんもこうしたギアボックスの事を知って欲しいと思う。
当たり前についているギアだけど、そう簡単なものじゃない。
こうした高い負荷に耐え得るものを造り上げると言う事は、皆さんが考えている程容易い事ではない。
設計から、素材から、製造まで、一貫して高い技術が必要だ。
特に製造の過程では、幾つもの工程があって、ちょっとやそっとじゃ出来上がらない。
切削や、研磨や、焼き入れなどの行程が山ほどあって、やっとの思いで出来上がる。
「すっげーなー!」
場数を踏んだ者には、ドキドキするくらいの景色に映ってしかるべきモノなんだ。
だからこそ、皆さんがギアを変えるシフトの操作では、丁寧な操作をするんだと私はいつも言っている。
価値あるものには、価値ある扱い方をする。クラシックカーを愛する皆さんの持つべき人格がそこにある。
かと思えば、いい加減なところもある。下の三つあるラバー製のいわゆるOリング。
これは、始動するスターターレバーのシャフトとシフトシャフトのものだ。
これなんかは、設計がまずく、暫くするとオイルが滲んでしまう。
言わばこの世界の誰もが知っているAMC製ギアボックスの常識だ。
本体のギア一式では感銘する程の仕事をしても、アウターカバーごときには大した配慮もない。
精力的に設計を変更すれば済む話と現代から見ればそうなるが、絶対に変えない。
伝統を、その時代の証を、後世に伝えて行くという絶対的な信念。それが英国製品の粋なんだ。
だから英国車は面白い。メードインイングランド万歳!!と私は言いたいんだな。
そして、こちらがプライマリーチェーンケースの内部だ。
オーナーの要望とを合わせて、今回はベルトキットを取り付けた。
科学繊維の織り込まれたラバー製のコグベルトにアロイ製のプーリーの組み合わせた。
たまに耳にする事に手入れが楽だと言う話を聞く。
しかし、メンテナンスフリーになるなどと勘違いも甚だしい。
本来ウエット状態で使うべきクラッチディスクをドライで使うのだから頻繁に清掃や点検が必要だ。
スチールのクラッチハウジングがアロイ製になってオイルもないのだから摩耗も急速に進む。
本来走行毎に手入れをするレース用部品だと言えば理解されよう。
年間の走行距離が延びる使い方ならば、スタンダードなウエットのものが適している。
クラッチケープルも含めて、定期的にメンテナンスを受けてほしい。
また、左側にある丸い発電用のステーターコイル。
本来の容量から40%程度発電能力の高いモノを取り付けた。
交換した点火装置を含めて充分な容量を確保している。
そして、完成したエンジン本体とギアボックスを車体に載せた。
何時の時にも、こうして苦労をした後、エンジンが完成する事は嬉しい。
一台一台その不具合にも違いがあって、施す作業もいろいろだ。
現代のコンピューター製の機械なら、もう少し効率よく仕事が進む。
言ってはいけない事だけれど、手間も時間も掛かるモノ。
それだけに、全てのエンジンの仕事を憶えている。
あの人のコマンドはこうだったな。この人のトラは、こうだったよ。
ひとつひとつのエンジンに、声を掛けてやりたい位の気になる私は、少しおかしいのかもしれない。
このエンジンのスターターレバーを踏み込むそのオーナーの為に、もうひと仕事する必要がある.....
布引クラシックス 松枝
1973 NORTON COMMANDO 850Mk1A 兵庫県K様 納車報告です。
1970 NORTON COMMANDO 750S 神戸市M様 納車です。
1969 NORTON COMMANDO 750 FASTBACK 修理作業記録 東京都T様
1971 Norton Commando 750 Roadster MkⅡ納車記録
1973 NORTON COMMANDO 850 Mk1A 納車整備記録 東京都世田谷区T氏
NORTON Commando 750 Roadster MkⅡ 1971 フルレストア車
1970 NORTON COMMANDO 750S 神戸市M様 納車です。
1969 NORTON COMMANDO 750 FASTBACK 修理作業記録 東京都T様
1971 Norton Commando 750 Roadster MkⅡ納車記録
1973 NORTON COMMANDO 850 Mk1A 納車整備記録 東京都世田谷区T氏
NORTON Commando 750 Roadster MkⅡ 1971 フルレストア車
Posted by nunobiki_classics at 20:56
│作業完成報告 ノートン編