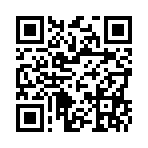2019年11月10日
1959 TRIUMPH T110 東京都W様 修理作業 プチ報告その6
東京都Wさんのワンテンの塗装作業、ツートーンのカラーと上塗り作業完了しました・・・
塗装を剥離し、亀裂や異常を確認し、数か所の溶接修理の後、下地を整え、パテを入れる。パテは中目を一度塗り乾燥させ研磨する。更に細目を塗り乾燥させ研磨する、更にグレージングパテを塗り乾燥させ研磨する・・・何工程もの作業があってそう簡単にはいかない。更に1959年製となればヘコミ以外に腐食もあるしノーパテと言う訳にはいかない・・・
前後のマッドガードも同じ、パテを含めると120番から始め最終的に600番まで研ぎをかけて行く・・・塗装とは一にも二にも下地作業の連続。暗く地味な仕事をずーっとやらなきゃならない。下地にある不具合は塗りが完了した時点で必ず表に浮き出で来るから絶対に手抜きは出来ない、それが塗装ってものなんだ・・・
次は下塗り作業だ。最近主流になっている2液性のプラサフを試してみたが・・・これは厚みをつけられて乾燥後の研磨の幅もあるし錆を押さえ込む力も強い。更に密着性も高く素晴らしく高性能だ。今ではどこの塗装屋でも使っているとの事・・・
只、仕上がりにゴージャス感は出るもののシャープさに欠けクラシックカー的には使い難い。性能よりも質感を重視したいと思うから私はやはり1液性だ。
ぺトロールタンクについているモノはメネジのネジ山に塗料が乗らない為に入れている仮のスクリュー、詰め物をするよりも遥かに効率が良い。
白を塗った。色はいわゆる「アラスカンホワイト」歴代のトライアンフが使用する馴染みの色だ。そして、ツートーンの境にマスキングをする。この1959年のT110とT120は色が違うだけで塗り分けは同じ。只、US仕様とUK仕様では幾分の違いがある。これはUKなので後端の湾曲部分がUSよりも穏やかになる。
そしてブラックを塗る。この順序は白よりも先に黒を塗る方が手間はかからない。が、モノのセオリーとしてはこうなる。
異物が付着しないように最善の努力はするが、やはり数点の「ホコリ」はあるし「ブッ」も発生する。乾燥させた後に1500~3000番程度のペーパーで取り除き最後はバフ掛けをする。上塗りの前に中塗りの表面を整える事は大切な工程だが、やり過ぎるとクラシックカー感は下がる・・・
そして、上塗りをした。このクリアー色にも1液性と2液性があって、その最大の違いは塗膜の厚みだ。1液性は薄くクラシックカーに最適な質感を得られる、反面2液性は後の磨き作業に耐えるだけの十二分な厚みが確保できる・・・
個人的には1液性を好む。もっともガソリンや紫外線やなにやらで現代人の価値観も変わってしまった。古いクルマやバイクが好きだと言ってるクセに塗装が薄くなるのは許せないと言う・・・そうした時、私は2液性のウレタン系塗料を可能な限り薄めに塗り、後のパフ掛けも最低限度に抑える。そうすれば耐候性を保ちつつクラシックカー的な質感を確保できる・・・
2液性のウレタン系塗料は常乾塗料ではないから加熱が必要、充分に塗膜が硬化した後、ゴールドでラインをひけば外装の塗装作業は全て完成だ。松枝
Posted by nunobiki_classics at
21:18
│作業中車両のプチ報告