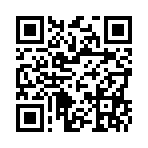2015年09月07日
1986 DUCATI 750F1 修理報告
1980年代に於いて最も刺激が強いと言えばイタリア製モーターサイクルに他ならない。その頂点とも言える「モンジュイ」。今もその筋では特別な存在だ。そのベースモデルである今回の750F1。1986年製のいわゆる2型、アルミ製タンクにドライクラッチ。生粋のドゥカティとしては最後のモデルになる。
以前、彼のF1をタイヤ交換した。懐かしさが込み上げてくる 「テクノマグネシオ」 このホイールに特別な思いの有る私は、何時もにも増して丁寧に組み込んだ。
「どう?エフワンは?・・・」 「ええ・・・すっごく楽しいです。高速道路を全開で加速するのが最高です!」
価値観とは十人十色、楽しいのならそれでいい。これからも大切にして欲しいと見送った・・・
そして、季節が幾つも過ぎた夏、私は彼のエフワンを引き取って来た。
「エンジンが、かからなくなりました・・・」
中を開けてスタータークラッチを見るとやはり磨耗が進んで使えない。部品は既にデッドストックだが思い当たるところがある。急遽海外へオーダーし、10日後に届いたスタータークラッチを交換した。
クラッチ自体は気持ち良い程に喰いつくようになったがセルモーターの調子が良くない。
そして分解してみた。 「・・・・・・・・・」
この際、出力もギア比も高いスーパーバイク系のモノに一式交換しよう。中古だから一旦分解整備した上で取り付ける。 「ギュンギュンギュンギュン・・・・」 充分過ぎる性能となった。
この後、他に異常がないか点検をする事にした。
ブレンボ社製の初代レーシングキャリパー。まだ混迷していた時代に於いて、それはそれは飛び抜けた存在だった。だが今となっては「古き良き時代の懐かしアイテム」 最早性能では叶わない。だが当時の最先端パーツに思いを馳せる時代の風情として、今のモノには決して代えられない。このキャリパー無くして1980年代のレースシーンは語れないんだ。
一昔前までレース専用部品だと思っていたモノは、今ではカスタムパーツの常連となっている。適合性や操作性など二の次、ギラギラと光り輝き自己主張できれば全て良し・・・それが時代の流れだ。だが、その多くにそっと目をやると、なんだか悲しくなるのは私だけだろうか?錆ついた軸を丹念に磨き給油をした。そして、この手のマスターシリンダーのその多くは、レバーの比率を間違えているものが多い。ガツンっと壁のように来る事が高性能なんかじゃない。自由度のある握り代がなければ高度なブレーキングは出来ない。「ギュ―ッ」と操作できる正常な状態に戻した。
チェリアーニの後を継ぐフォルセライタリア製のこのフロントフォークもこの時代に於ける通好みなアイテムとしては欠かせない。丸みを帯びたボトムケースにゴールドアルマイトのシールホルダー、双方ともに調整可能なダンパーシステムなど、どれをとっても超一流だった。
これはハイドロキットと言っていわゆるダンパー本体で総アルミ製。小さくて見難いが上部(右端)に小さな穴がある。これが伸び側のダンパー調節用のオイル穴だ。
そしてこれがその相手側で下に径の違う穴が幾つか見えると思う。この段階的に違っている穴でもって流れるオイルの移動時間を調整する仕組みだ。伸び側の調整ダイヤルは5クリック。何も考えずに組み立てると、まともに作動しなくなるので注意が必要だ。
今度はコンプレッション側だ。左下にある黒くアルマイト処理されているモノをアンチダイブバルブと言ってこれにも大きさの違うオイル穴が開いててそれを回転させる事で流量を調整する。この圧側の調整ダイヤルは3クリックだ。
長さが違っていたスプリング用のカラーと座金を製作し、更に軽量なオーナーの為にレートを変えたスプリングを取り付ける。元々摺動する抵抗の強いフォークなので過度なレートの低さは逆に動きを妨げる。丁度の塩梅を模索する為に幾つかスプリングを用意し選択する作業が必要だ。
垂れるほどにオイルが漏れるダンパーや油圧のイニシャル装置。見事なまでに色褪せたリアショック一式・・・。こうしたパーツは日々の手入れや定期的なメンテナンスがあって初めて機能する。残念ながら一度取り付けたら後は知らない的な状況が今日では一般的だ。
皆さんはこうした究極のレース用パーツの聖地とは何処かご存知だろうか?それはドイツでもなくアメリカでもなくイタリアでもない。今も昔も英国だ。F1やモトGPを初めとする世界各国の超名門レーシングチームがこぞって本拠地を構えるこの国にはレベルの高い下請け工場やエンジニア達が現存且つ継承されていて世界の頂点としてゆるぎない地位を築いている。東京大田区や東大阪市の町工場の如く、世界最先端のモーターレース用パーツはイギリスの町工場なくして出来得ない。その英国が生んだ最高品質なサスペンションがこの「ナイトロン」なんだ。
ナイトロンジャパンさんより空の本体を借用し寸法等を決め特注した。このショックの特徴はガスを入れた後もフリーに動かせるリザーブタンク用のホースだ。スペース的に何かと制約のあるモーターサイクルの場合大変重宝する。取り付け位置を変更する場合にもホースに過度な負担を掛けずに正しい位置に配する事が出来るのは他社には無い機能だ。そしてスプリングは当然ながら軽量なオーナーに合わせレートを選択し、走行後に再度検証する。
このブラケットは他車のモノを加工して取り付けてあるがとても褒められた仕事ではない。手やすりで荒く削った跡は歪に放置され、更にハンドルストッパーの機能が無くメーターやタンクにガンガン当る。これではどうしようもないので、適切に止まるストッパーを製作した。次にハンドルロックの機能も無いので、ステアリングステムにフライス盤で長穴加工を施し施錠を可能にした。双方とも一般公道用として最低限度やるべき事だ。
極めつけだこれだ。怪しいとは思ってはいたもののグリスが皆無だとは・・・幾ら低速で廻るステアリングだからと言ってもこれは辛い。何をしようが構わないが 「素人整備」 だけは止めた方が良い。この世に命とは、たったひとつしか無いんだ・・・
次はリアのスイングアームだ。ここにも大きな不具合がある。手で揺するだけでガクンガクンと酷いガタがある。こりぁ怖い。抜いてみるとブッシュと軸の磨耗はそうでもない。ところが有るはずのスラスト側のブッシュが無く、入っていたのはエキゾーストパイプ用のガスケットが一個のみだった。只、この時代のドゥカティのここは設計も未熟で、今の形になるまで結構な変更を受けている。当然パーツもデッドストックだから、そのまま放置されている事が多い場所だ。
今回は少し考えるところがあったので手持ちの硬いジュラルミンを旋盤で削り一度様子を見る。軸の左右に光っているものがそれだ。幾らか走った後、正確なモノを砲金にて作る予定だ。
恐らく社外品に変えられているこのFRP製カウルはすこぶる薄い。しかし、このレーサーと同じように薄く積層されたカウルは超魅力的だ。エキゾーストパイプの高温から幾らかでも守ってやりたい。剥がれて肝心な部分が無くなっている断熱材を形に沿って作り直した。
たったこれだけの事、皆さんも良く知っている至極基本的な事だけれど、大事なことはこれは恒久的な処理では無いと言う事。劣化や不具合が見られたならばその場で即張り替えるものだという意識を持つ事、レーサーとはそう言うものなんだ。
こうした入手し難くなったパーツも、やはりそれ用のモノが美しい。代替品が適当に入れられているよりもこうしたジェニュインなモノを優しく取り付けてやりたい。この絵を見てオールドドゥカティの 「粋」 を感じとれる皆さんは相当ドゥカティが好きなんだ・・・
このバッテリーの位置は通好みだ。シートカウルから頭だけ覗かせてサーキットを疾走するその雄姿に皆が興奮した、しかし・・・
「重いものが中心から遠くに有るほど車体へ悪影響を及ぼすぞっ!」
「重量を中心に集めるのが常識だろう!・・・」 分かる、だがそれは今の概念だ。
こうした過渡期である1980年代の姿にこそ 「んー、良いね!」 多くの感動と哀愁が漂っているのさ。
その他多種多様な作業を終た後、エンジンをかけようとするもガソリンが落ちて来ない。見ると塗装のネタがリザーブ側の穴を塞いでいる・・・普通、燃料タンクを塗装をするのに内側にはマスキングしないものだろうか?。タンク内の劣化した塗膜を全て除去し、コックも全て分解し対処した。
因みに、スタンダードの燃料コックは使い勝手が悪いのでこうしてメインとリザーブの切り替えが一体になったモノに交換される事が多い。だがその流量が極端に小さくなる。マロッシの42口径を装着したこのマシンには役不足、コックの選択には注意が必要だ。
そして検査受けの為、魚崎の陸事に出掛けた。順調に検査を終え戻ろうと車体を押して歩いていると 「しかし、小さいなぁ・・・」 750の市販車としては異例のサイズ。こんなにコンパクトな750は二度と製品化されない、それだけは断言できる。
サスペンションに当りをつける為に走った後、調整作業に入る。車高、イニシャル、ダンパー等 軽量な彼を想定して進めて行く。難しいのはこうした古いイタリア製品では現行品のように必ずしも一定した数値にならない事だ。それを加味した上で幅を持ち、一歩ずつ目標に導いて行く事がある意味古典的サスペンションを仕上げるコツになる。
では走ってみよう・・・(※今回は危険なので走行中の写真はありません・・・)。
「ドゥッォ――ン・・・ドゥダダダダダダダダ・・・・」
セカンドギアからトップギアまでスロットルを適切且つ大端に開けて加速する。
「ドゥオオオオ―――ン!・・・ドゥオオオオ―――ン!・・・ドゥオオオオ―――ン!・・・」
そしてコーナーが見えた。自分の足の位置、上腕、頭の位置・・・ブレーキングに備えて体勢を整え神経を集中する・・・ブレーキングはモーターサイクルに乗る上での要だから、必ずちゃんとやる。ここでミスをすると必ず後に尾を引くから絶対だ。
「ドゥオオオオオオオ―――ン!・・・・・・・ズゥ―――ン・・・ズゥ―――ン・・・ズゥ―――ン・・・ヒュルヒュルヒュルヒュル・・・」
イイ感じに倒し込んだら目線を移す。旋回中は下半身でマシンをコントロール。決めたポイントを抜ける頃スロットルを大端に開けて行く・・・
「ドゥオオオオ―――ン!・・・ドゥオオオオ―――ン!・・・ドゥオオオオ―――ン!・・・」
立ち上がりは猫のように小さく背を丸め身体全体でマシンをホールドし目が覚めるような加速をしよう・・・
「ドゥオオオオ―――ン!・・・ドゥオオオオ―――ン!・・・ドゥオオオオ―――ン!・・・」
あっという間に直線が底をつき、次のコーナーが迫り来る・・・
「・・・ズゥ――ン・・・ズゥ――ン・・・ズゥ――ン・・・ヒュルヒュルヒュルヒュル・・・」
私は彼のマシンに跨り、サスペンションの動きに神経を研ぎ澄ませ、ずっとずっと走り続けた・・・
何をやっても明確な反応が無く、只怖いだけの状態だったものがどう変わったのか?・・・うん、やっとブレーキングから倒し込みの動作が鮮明に理解出来るようになった・・・レバーを緩めてから倒して行く過程を身体で感じられるようになった・・・
今まで不安定だったコーナーの中央付近、じーっと頬の下に路面を感じながら旋回しその時を待つ事が出来るようになった。今まで不快だった立ち上がりも何も怖いものが無くなった・・・自分の意思に沿ったコーナーへの進入と、ジワーッと持ちこたえられる旋回中、キラッと輝く出口への爽快な加速感・・・全てが自分の意思で操れるようになる・・・走る事が楽しくなった 「そう・・・これなんだっ!」
そしてオーナーのG氏に工場に来てもらい一連の乗り方を伝えた。ふたりで身体を使い、こうして、ああして、ととっかえひっかえ乗り換えていろんな事を話した。見ていると彼はこのマシンが相当に好きなようだ・・・くどい私の話はもうよして、少し離れて彼を観察した・・・
きっと彼の回りにはいろんな事があるんだろうな・・・・光り輝く人生ばかりじゃなかろう・・・きっと辛い事も嫌な事も投げ出したくなる事も沢山有るはずさ・・・彼の横顔にそれが書いてある・・・
けれど、何も心配なんてしなくていい。誰だって人生は楽しい事ばかりじゃない。前に進むことばかりが人生じゃないさ。人間って本当は弱いモノなんだ・・・。
それでも君はラッキーじゃないか。この軽く輝ける小さなマシンに出会える事ができたさ。どんな時にもこのマシンを見れば気分が落ち着く・・・どんな時にもこのマシンに跨れば鼓動が高鳴る・・・どんな時にもこのマシンと風を切れば夢中になれる・・・そんな誰よりも幸せな君がそこに居るじゃないか・・・
私がこうしてイタリア車を全力で整備するその訳は、只単に機械を直す事なんかじゃない。
「このマシンがなければ生きて行けない・・・」 それ程までに彼はこのマシンを愛している。
だったらそれに応えてやらなきゃならないさ!
私の握るスパナ1本でひとりの人生が左右されるんだ・・・
だからこそ誰よりも腹をくくり! 誰よりも気合いを入れて! 何処のどいつよりも根性をもってやり抜いてやる!それが私のやり方だっ!
彼のマシンに丹念にワックスをかけ磨いた後、彼は帰る身支度をした。
外は生憎の雨模様・・・本当はスッキリと晴れて、二人で清々しい気持ちになりたかった。
気をつけて帰って欲しい・・・事故の無いように帰って欲しい・・・
だって君の素晴らしい人生ってのは、これからじゃないか・・・
1986 DUCATI 750F1 修理記録 オーナー神戸市北区 G氏
一般道走行距離 252.5キロ
高速道路走行距離 82キロ
総走行距離 334.5キロ
1986 DUCATI 750F1-3 一般修理作業報告 西宮市T様
1955 BMW R50 神戸市 Y様 車検整備
1989 DUCATI 900SS プチ修理しました。
1972 HONDA CB750K1 新たなオーナーの下へ!兵庫県N様
1980 HONDA CB750FA エンジン修理作業報告
1971 HONDA CB750K1 整備報告 オーナー 大阪市帝塚山 H様
1955 BMW R50 神戸市 Y様 車検整備
1989 DUCATI 900SS プチ修理しました。
1972 HONDA CB750K1 新たなオーナーの下へ!兵庫県N様
1980 HONDA CB750FA エンジン修理作業報告
1971 HONDA CB750K1 整備報告 オーナー 大阪市帝塚山 H様
Posted by nunobiki_classics at 14:33
│作業完成報告 その他