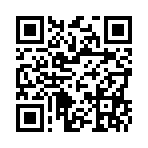2011年07月09日
初めてのプログ 忘れはしないあの時のトロフィー・・・
これは、1960年のトロフィーだ。
私の下に来た時にはそれは酷かった。
恐らく専門のショップではないところで、その場しのぎの作業を受けている。
ミリねじで切り直され、日本製の部品が混在するトライアンフを凝視した。
それは、まるで亡骸のように私の目に映った。
冷たい雨に打たれ続けて耐え忍んでいたこの子は、自分を守ってくれる素敵なオーナーが現れてくれる事を未だか未だかと待ち望んでいたはずだ。
そう思うと私は悲しかった・・・
「よくここに来たなぁ。もう安心しろ・・・」
人間の都合によって簡単に捨てられる。
私が強く言いたい矛先は、彼らの気持ちを踏みにじっている貴方達・・・・なのかもしれない・・・
ここから始まった修復作業。
1年をかけ出来上がったものがこの写真のトロフィーだ。
皆さんにも見えるだろう、この子の満面の笑みが・・・
「良く頑張ったなぁ・・・もう好きなだけ走っていいんだぞ・・・」
その時、私には見える。
次の素敵なオーナーと一緒に風を切り、懸命に走っているこの子の姿が・・・
「綺麗になったなぁ。君ならきっと大切にしてもらえるさ、頑張るんだぞ・・・」
こうしてまた1台のトライアンフが生涯忘れられぬものとなっていく・・・
布引クラシックス 松枝
以前アップしたTR6をもう少し詳しく書いて欲しいとの事で再度報告してみようと思う。
これは、フレームを単体にして亀裂、曲がり、変形、摩耗などの不具合を調べ修正しているところ。
スイングアームのある車体はそれも調べ、ステアリングも同様に完全に調べる。
有るべきものが無かったり、逆に無いはずのものが有ったりと結構な知識を持ってあたらないと大きなツケを払うことになる。
只のパイプのように思うだろうが、ここは手の抜けない大切な部分だ・・・
ホイールにタイヤを入れてほぼ仕上がった車体。まっすぐにシャキッとしたフレームは美しい。
ペイントも最近のレストアブームではパウダーコーティングが主流のようだが、うちではこの時代の英国車にそれは使わない。
理由は美しいフレームの接続部や肌目が消えのっぺりとしたものになってしまうからだ。
それなりに価値のある車体にこそこだわりを持ってやるべきかと思っている。
分解中のトロフィーのクランクシャフト。
この研磨されたシャフトの先端と、タイミングカバーの黄色いブッシュが分かるだろか?
ここが少しばかり大切な部分になる。コンロッドの大端部とシリンダーの潤滑を担う大切なオイルラインの接続部分だ。
双方が金属同士。どこにもラバー製のシール材などない。クランクシャフトは高速で回転している・・・・
精度などあってないような英国製の部品を何も考えずに取り付けても、暫く走るには問題は出ない。
しかし、ずっと大切に乗って頂きたい。何の気兼ねもなく積極的に実用してもらいたい。
そうなると経験というさじ加減が必要になってくる・・・・
クランクピンの研磨が済み、大端部のオイルクリアランスも完全にとっている。
ここは何があっても妥協はしない大切な部分だ。クランクシャフトの振れも100分の1ミリ単位でOKだ。
そして、オイルラインの清掃も済んでいる。
このチューブのシステムの良否は別として、時として多量に溜まるスラッジは、こういう機会に全て取り除くことが賢明だ。
このトラのクランクシャフトは軽量で耐久性もあってなかなかの優れものだ。
軽すぎて鼓動感が薄れていることもない。
多くの発想が混在するこの時代に於いて、スタンダードで使える上質なクランクシャフトだと言えると思う。
また、写真に見えるドライブサイド側のメインのベアリンク゛。ローラーのものに変更するのが定石だ。
ボールベアリングとはボール一個に対して四ヶ所の点で支持される。
こいつは2か所の長い線接触となり、おおむね玉数も多くなる。耐久性が上がることは見ての通りだ。
そして、軸方向への自由度ができる事はそれ以上に大切な要素だ。
こうして仕上げたクランクシャフトをケースに納め、車体に載せる。この時ばかりは更に気合いが入る。
折角積み上げてきた今までの作業を生かすも殺すも組み方次第。
特にこのプリユニットでは各部の剛性が極端に低いので尚更だ。
いろいろやってかたちになった時にはお客さんの顔か浮かぶ
・・・・いいものに仕上がりましたよ・・・・・と。
この感覚がお分かりだろうか?整備とは何もエンジンを触るだけではない。
地道な仕事にも大切な要素が潜んでいる。
「何を大げさな事を・・・」と考える人は、ここにはいないと思うが・・・・
これはいわゆる8本スタッドのシリンダーヘッド。元の車体のオリジナル品だ。
今回のものは、亀裂等も無く良いものだった。うちではバルブガイドにプラス製を組む事が多い。
理由は幾つか有るが、熱伝導率の高さが魅力だからだ。逆に耐久性が欲しい場合は鋳鉄製を選ぶ。
言いたくはないが、ここに本来は無いオイルシールの話がよく出る。今の時代から考えると当たり前の話しだと思われるだろう。しかし、私は依頼が無い限りその加工はしないし、薦めもしない。
シールが無くても丹念に組んだエンジンならば使用に差支えるような不具合が出ることはない。
オールドブリティッシュモーターサイクルを楽しむ意味を考えて欲しい・・・・・。
バルブシートは鋳鉄製。シートカットを含めバルブ一連の作業は完璧だ。
写真の感じであたりが少し狭く写っているが、この幅が重要になってくる。美しく仕上がっている状態がこれだ。
因みに、この時代のこの大きな燃焼室。
これを完全に燃やすのは容易い事ではないが、上手なスロットル操作をもってすればこの上ない楽しさが味わえる。
これは、トラのギアボックスだ。細部まで不具合が無いか調べ丹念に組み上げる。
英国車風の現代のバイクに乗って何かが違うと私の下を訪れる人は多い。
しかし、ギア比に気を向けていた人は皆無だ。
早く走る事と、楽しく走る事とはまた別の話。今こそ4スピードギアを楽しむ時ではないだろうか・・・・
丹念に仕上げたギアボックスが、高いレベルに仕上げた車体に載る。
美しく組みあがっていく様はトライアンフならではだ。
ほぼかたちになったプリユニットエンジン一式だ。この姿勢の良さがトラの魅力だ。
前後のマッドガード、チェーンカバーにショックアブソーバー。サイドスタンドにセンタースタンド。
全てが上質に取り付けられていることが分かると思う。
特にスタンドの類は、摩耗があってしっかりと立たない車体が多い。
今のバイクではスタンドの不具合など皆無と言ってよいが、この時代のモーターサイクルでは使いものにならない状態は相当数ある。ご自分のものも一度見てみると良い・・・・
ドライブサイドから見たプライマリーチェーンケースの内部。
ここは元々の強度や耐久性が低いだけに常に完全な状態にする必要がある。
組み立てるのもエンジン、ギアボックスそしてフレームとの絡みを取りながら行う丁寧さが必要だ。
今回のオルタネーターには、10アンペアの充分過ぎるものを取り付けている。将来的なものも含めての選択だ。
うちでは使用する電力に応じて、必要な容量のものを計算し取り付ける。
こればかりはオリジナルにこだわるよりも、走って帰れる事の方が大切だ。
特にバッテリー式の点火装置へ換装した場合の計算は必須だ。
また、スマートで格好の良いダイナモ車のカバーも分かるが自分の力量に応じて選択して欲しい・・・・
これは、電装関係の作業中だ。オリジナルのメインハーネスを使えば作業も簡単だ。
しかし、オーナーからの依頼事項が多い場合は結果的に太くなってしまうので一から引きなおすことになる。
スマートな配線は何も格好が良いだけてはない。無造作なものを作れば必ず不具合が起こるものだ。
そして、オリジナルの配線色と同じにすることは、次に作業をするメカニックへの礼儀だ。
これが、通常の機能にフラッシャー、モディファイした充電系統、マグネトーと電装系を同時に開閉できるようにしたメインキーなどの回路を追加し完成したハーネスだ。極力無駄を省いているので、非常にコンパクトになっているのが分かると思う。
もちろん動きのある場所ではそれも考慮している。
同時に開閉できるメインキー?・・・・・・・そういう事になる。
良く言われる配線の接続端子。これも意見が有ると思う。しかし、なま鉄を使った英国製のものは良く折れる。
これは事実だ。今回のように見えないところには日本製を、見える部分には英国製を使う。
実用性と雰囲気を天秤に掛けて決めればよい。
大切なことは年式や状況、その車体の価値にオーナーの意向を踏まえ最良のものを作って差し上げることだ。
当時の充電能力とは、夜間走行では消費電力の方が上回り、バッテリー電圧が下がり続けることも普通にある。
よく信号での停止時には、ライトスイッチを切って欲しいというのは少しでも消費を抑えるためだ。
そのまま下がり続けていけばバッテリー点火式の車両は最終的に走行不能となる。
そのことを考慮してもう一度この数値を見てほしい。エンジン回転数は約3500、かつ安定した制御がなされる。
無負荷ではあるが標準ではありえない数値だ。ヘッドライト点灯時にも13ボルト弱は確保している。
このことを素人のお客さんに言っても何の事か分かりにくいと思うけれど、普通にトラを買っただけではこうはならないと知って欲しい。
これは、ご存じのイギリスはスミス社のクロノメトリックのスピードメーターだ。
1960年過ぎまで実用されていたものだ。みなさんご存じなので改めて言うのも何なのだが、私も大好きだ。
ギアで掻き揚げられて進む針の動きは、今から考えると相当不便で瞬間的にはどこを指しているのか全く分からない。
急減速でもしようものなら針は固着して動かなくなる。
レヴカウンターならば更にその動きも慌ただしくなるが、信用性などあったものじゃない。
こんないい加減な計測器が今のメータ-にあるだろうか?
その一連の動きは見ているだけで微笑ましくなってしまう。
じーっと見つめているとガラスの向こうに当時のロマンが見えてくる。
逸品とはこういうことを言うのではないかと思う・・・・
今回購入頂いたオーナーは趣味性の高いお洒落でダンディーな方だ。
かのスティーヴに対する強い憧れを持つ。
「外装はこのイメージにして欲しい。」手にする洋書には泥まみれになったスティーヴの絵があった。
その眼は真剣だ。年式の違いはあったが私も賛同した。この熱意に負ける訳にはいかない。
ようやく完成したトロフィーを初めて外に出す。うす汚いうちの店でも、この時ばかりは爽やかな空気感に包まれる。
エンジンを始動し、各部を点検調整しているところだ。
うちでは、レストアや完全な分解作業後には必ず試運転を行い、手直しをしてから納車をする。
夏は日本海の経ヶ岬、冬は赤穂御崎まで出かける。
距離は300~400キロになるので軽いものではないが、市街地から高速道路までいろいろな状況を試す。
そうして戻ってきてから再度手直しを行い仕上げる。距離を走り手直しをする事。これが相当大切なことになる。
古い英国車の作業に於いて、工場の中だけで分かったような顔をするには10年は早い・・・・。
7月の真夏に兵庫県の日本海側にある竹野海岸を目指した。
いつも試運転では様々な道を選択して走る。安直な道を選んだりはしない。
そして私は素人に化ける。なぜなら多少の不具合ならば小手先で上手く操ってしまうからだ。
不調で止まりそうなエンジンでも右手一本で正常に走らせて帰ってきてしまう。これでは意味が無い。
乗る人は一般の方。だから玄人であってはならない。わざと不器用に乗って不具合が出るのを期待する。
早朝に出発し淡々と走り続けた・・・・・
そしてここは兵庫県民である私が兵庫県で最もお気に入りの場所のひとつとしている竹野海岸のとある小さなバス停だ。
ここで碧い夏の日本海を眺めるのが好きなのだ。
小型の携帯ストーブでお湯を沸かし、お気に入りのコーヒーを呑みながら自身のスイッチをオフにする。
外気温は35度もあるというのに、静かで涼しげなそよ風が心地良い・・・
この老兵と共に「遠くまで来たんだなぁ・・・・。」
何時になってもそのことが嬉しさとなり心を打つ・・・・・
一日走り続けて陽も暮れてしまった。最後に試す高速道路を走る。
西紀サービスエリアで休息し、間もなく試運転の一日が終わった。
総走行距離は400キロ。燃費も25キロ程度と調子の良さが伺える。
翌日に点検を行い各部の確認と調整をする。最後に洗車を行いワックスを掛け丹念に磨いた。
「売るのをやめてこのまま手元に置いておこうか・・・・」
スクリュー一本にまでこだわり続けた車体に愛着が湧かないはずが無い。
「いつか戻ってきたら面倒見てやるから安心しろ・・・・」いつも心の中でこう言って別れを告げる。
もうここから先には私の出来る事はない。後はオーナーの力量に任せよう。
先ずは機械を理解しご自身も成長されることだ。
1960年に作られた世界の逸品に敬意を表して、多くの愛情を注ぎ込んで頂ければきっとそれに応えてくれるはずだ。
こうやってまた一台、オールドブリティッシュモーターサイクルが街に出ていくことが私の喜びでも有り使命だと思っている・・・・
1960TRIUMPH TR6 神戸市N様 車検整備致しました。
TRIUMPH TROPHY SPECIAL 車検整備 大阪堺市M様
1975 TRIUMPH T160 TRIDENT 東京都H様 納車のご報告です。
1965TRIUMPH T90SC PROJECT 兵庫県H様
1965 TRIUMPH T120 BONNEVILLE 納車整備記録
TRIUMPH TROPHY SPECIAL AMAL 389 堂々と交換致しました。
TRIUMPH TROPHY SPECIAL 車検整備 大阪堺市M様
1975 TRIUMPH T160 TRIDENT 東京都H様 納車のご報告です。
1965TRIUMPH T90SC PROJECT 兵庫県H様
1965 TRIUMPH T120 BONNEVILLE 納車整備記録
TRIUMPH TROPHY SPECIAL AMAL 389 堂々と交換致しました。
Posted by nunobiki_classics at 12:44
│作業完成報告トライアンフ編
この記事へのコメント
やっぱり英車はイイですね!カタルシスがあります。ブログ更新お疲れ様です!
Posted by カスタムインフェクションMJ at 2011年07月09日 12:59
at 2011年07月09日 12:59
 at 2011年07月09日 12:59
at 2011年07月09日 12:59